一人社長の賃貸社宅について
東京都で IT 系の小規模法人を経営している代表取締役です。現在、都内にある鉄筋鉄骨造・築 30 年ほどの1LDK(延床は 30 ㎡弱)の賃貸物件を、法人名義で契約し社宅として利用することを検討しています。インターネット上では「役員が家賃の1~3割を自己負担すればよい」という説明を多く見かける一方で、顧問税理士に軽く相談したところ「原則は 50 %負担」と言われ、どちらが正しいのか判断できずに戸惑っています。実務上の一般的な自己負担割合を教えていただけないでしょうか。
あわせて、物件が購入ではなく賃貸であっても、法人契約にさえしていれば社宅扱いにするうえで特別な問題ないでしょうか。もし注意すべき要件や手続きがあるようでしたらご教示ください。
また、私には都内で一人暮らしをしている弟が二人います。彼らは会社の役員ではなく、たまに業務を手伝ってもらう程度で、給与は支払わず食事を奢る程度の謝礼しかしていません。このような家族の住居についても法人名義で契約し、社宅あるいは福利厚生費として計上することは認められるのでしょうか。もし可能であれば、必要な手続きや留意点を教えて頂けませんでしょうか。
上記、ご教示いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
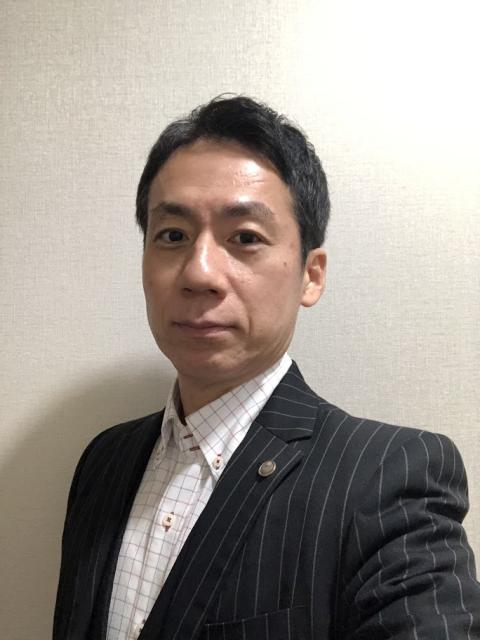
岸川祐次
原則として、役員に対する社宅の現物給与としての課税を避けるためには、一定の家賃を役員から徴収する必要があります。この徴収すべき家賃の計算方法は、賃貸物件か持ち物件か、また物件の広さや構造によって異なります。
ご質問のケースは「都内にある鉄筋鉄骨造・築 30 年ほどの1LDK(延床は 30 ㎡弱)の賃貸物件」ですので、この場合の役員が負担すべき家賃(以下、「賃貸料相当額」といいます)は、一般的に以下の合計額となります。
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2)+ 12円
2.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.2
3.賃借料(会社が支払う家賃) × 12分の1
そして、税務署は、役員からこの「賃貸料相当額」の50%以上を徴収していれば、原則として現物給与とはみなさないという取り扱いをしています。これが顧問税理士の方が「原則は 50%負担」とおっしゃった根拠と考えられます。
一方、インターネット上で見かける「1~3割の自己負担」という情報は、上記の「賃貸料相当額」に対しての割合ではなく、会社が支払う家賃に対しての割合を指している場合が多いようです。
したがって、実務上は、まず上記の計算式で「賃貸料相当額」を算出し、その50%以上を役員の方にご負担いただくことが、現物給与課税のリスクを避けるための一般的な対応となります。
ただし、物件によっては「賃貸料相当額」が会社が支払う家賃の数割程度になることもあり、結果的に役員の自己負担割合が会社が支払う家賃の1~3割程度になることもあります。
結論として、安全なのは「賃貸料相当額」の50%以上を役員にご負担いただくことです。
法人契約の賃貸物件の社宅扱いについては物件が購入ではなく賃貸であっても、法人名義で契約していることが社宅扱いとするための大前提となります。
社宅として認めてもらうためには、以下の点に留意する必要があります。
1.賃貸借契約の名義が法人であること。
2.役員から上記で述べた「賃貸料相当額」の50%以上を徴収していること。
ご兄弟は会社の役員ではなく、たまに業務を手伝ってもらう程度で給与も支払っていないとのことですので、原則として、ご兄弟の住居を法人名義で契約し、社宅や福利厚生費として計上することは難しいと考えられます。
社宅は、原則として役員または従業員に対する給与の一部とみなされるため、給与を支払っていないご兄弟を対象とするのは適当ではありません。
また、福利厚生費として計上する場合、その対象は原則として「従業員全体」に向けられたものでなければなりません。特定のご家族のみを対象とした住居の提供は、福利厚生費とは認められにくいでしょう。
もし、ご兄弟に業務に対する対価として給与を支払うのであれば、従業員に対する社宅として検討の余地は出てきますが、現状では難しいと言わざるを得ません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年05月11日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。























