ペアローン戸建の売却利益に対する確定申告について
ペアローンで住宅ローンを組んでいた戸建を、離婚をきっかけに売りに出しており、ようやく買付が入り、210万円ほど売却益が発生することがわかりました。
自分と元妻とで持分は3:1です。
以下の対応案は成立するのか、どのようにすればよいのか、教えていただけませんでしょうか。
※離婚後、互いに接しない距離に住んでおります。また売却益以外に、アンダーローンになって手元に残る現金は慰謝料代わりに私(旦那側)がもらう離婚協議書面を既に交わしています。
質問①:売却益を3:1に分け、それぞれで好きなように(3000万特別控除の適用有無)対処すればいいと思っていますが、その場合に、互いに顔を合わさずに、物件取得費用として計上できる各種領収書と、購入時の売買契約書をどのようにして自分と元妻の手元に渡るようにすればよいでしょうか。領収書および売買契約書は、一方が原本、片方がコピーでも確定申告できるのでしょうか。
質問②:質問①の対応が難しい場合に、売却益に対する税金対応を全て
私が実施することでも問題ないのでしょうか。(例:私は確定申告を行い、元妻はこれに関する対応を一切しない、など)
質問③:離婚協議書にて、売却益及びアンダーローンで売却できた場合の現金は旦那側とする旨を約束していますが、この書面があれば、差分が旦那側口座に振り込まれることによっての贈与税の発生等はないとの理解でよいでしょうか。もし贈与税発生可能性があるとすれば、どのような対応をしておけばよいでしょうか。
住宅売却に関する対応は、仲介不動産に任せておりますが、確定申告を実施するにあたり、私は元妻とできるだけ顔を合わせたくありません。また、脱税する気は全くありませんが、節税できるところは節税したい意向です。
長文で申し訳ございませんが、知見をお貸しください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
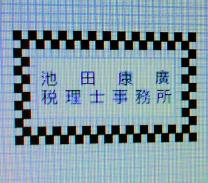
① 一方が原本、他方がコピーを所持し、確定申告すれば結構です。
⓶ 共有物件の譲渡であることから譲渡所得はそれぞれに発生します。よっ
てひとりの所得として申告することはできません。
③ 売却益を3/4・1/4に分割することが原則ですが、この割合で分割
した金額と実際に分割した金額の差が110万円を超える場合は超えた部
分について贈与税が課税されます。この約束が「贈与します。」「受贈し
ます。」という贈与契約の成立ということになります。贈与税が課税され
ないようにするには、さきに述べた割合で分割した金額と実際に分割した
金額との差を110万円以内にすることです。または、この差額を「慰謝
による慰謝料」ということにするのであれば、贈与税の課税はありません
早速の回答誠にありがとうございます。
②に関しては、①にてコピー対応できるとのことでしたので実施不可でも問題ないとの理解となりました。
③に関して、更問です。
「売却益」…税金の発生する利益、約210万
「利得分」…税金の発生しない、返済が進んでいたことにより、売却価格と残債との差分で発生する利得分、約800万
と仮に定義します。
「売却益」については、回答いただいた内容で大筋理解できたと思います。
「利得分」についても教えてください。
元妻との離婚協議書においては、「利得分」についても全てこちらで受け取ることとして記載しております(子供をこちらで養育することもあり養育費と慰謝料を兼ねる意図です)。
質問2-①
約800万受け取ることによる、贈与税を回避する方法は、先ほどの回答と同じでしょうか。
質問2-②
決済の場での銀行担当者への依頼として、売上金の振込について、「妻口座には残債をちょうど払い切ってゼロになるところまで入金」「私の口座にはその他全部を入金」というような依頼でよいのでしょうか。
恐れ入りますが教えてください。
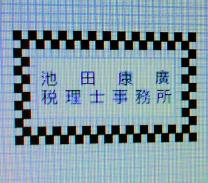
①登記持分について、どのような根拠で決められたか不明ですが、ローンの毎回の返済を登記持分の割合でしていたとして説明します。・・・とすると、「利得分」800万円の各人の分配額は夫600万円妻200万円ということになります。この800万円を御主人が取得した場合、本来は200万円を妻から御主人に贈与したことになります。しかし、この200万円を財産分与及び慰謝料として取得するのであれば、前回も回答しましたが、本来課税される贈与税は非課税となります。
⓶妻口座には(譲渡価額-残債額-譲渡費用)× 1/4 の金額を振り込むことになります。ここでいう譲譲費用=仲介手数料+登記料+ローン返済関係費用で、譲渡所得の計算上の譲渡費用とは金額が異なります。(譲渡所得の計算上、ローン返済関係費用は譲渡費用とはなりません。)
更問にまで丁寧に回答頂き大変助かりました。教えて頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2022年10月23日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






















