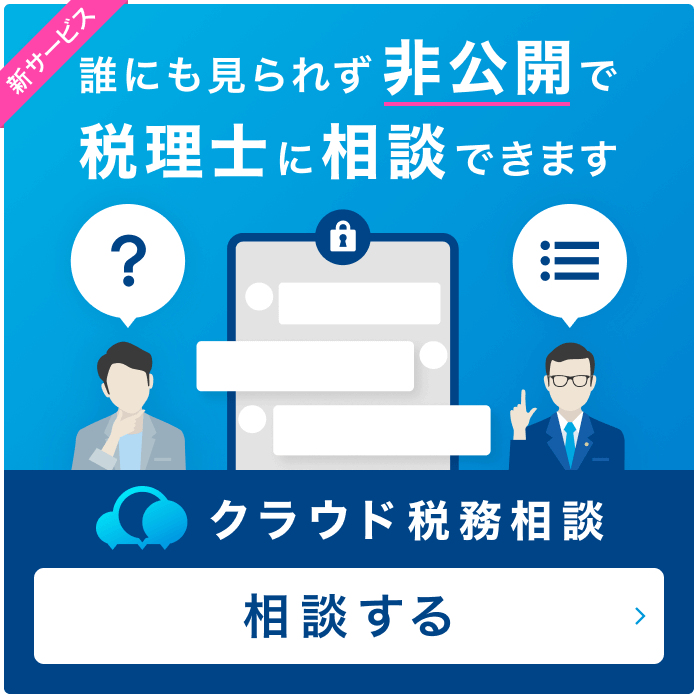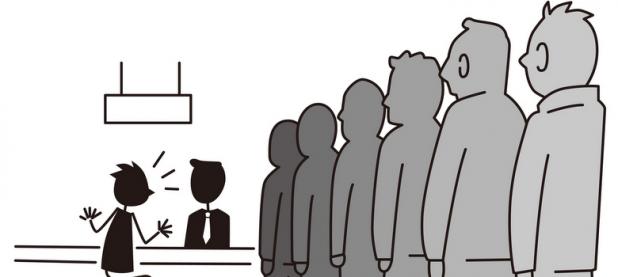遺留分減殺請求に関する課税について
標記の調停が以下の条件で成立した場合の課税(贈与税)の有無、もし課税される場合はその基本的な考え方についてご教示ください。遺留分減殺請求は相続時点と同時にされたと考えてください。
条件 相続人はA及びBの2人。遺言によりAはBの遺留分を侵害。調停成立は相続から2年経過時点。
Aの侵害額5000万円。Aは相続した評価額6000万円の収益不動産をBに返還することで合意。上記返還額と侵害額の差額は1000万円。この差額を下記の税引後の利益で相殺することで合意。
Aが相続後調停成立までの2年間に同不動産から得たの所得(各種税の納付後、ローン返済後のキャッシュ)は1000万円(500万円/年)。2年間のローン返済、所得税納付はAが実施。
<質問内容> 以上の場合、Aが得た収益不動産からの上記所得1000万円はBからの贈与と見なされ、贈与税を支払う必要がありますでしょうか。(法律では減殺された資産は相続時点からBの所有になり、その後の成果物はBに帰属しますが、本例では返還額が侵害額より大きい特別なケースです。)
よろしくお願いします。
税理士の回答
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合には、相続時点に遡り、一方は、「更正の請求」、他方は、「修正申告」をして所得を精算します。贈与税の課税対象にはなりません。
詳しくは、国税庁のホームページを参考にしてください。
「遺留分減殺請求があった場合の相続財産から生ずる所得の課税関係について」
福田 知弘
研究科第39期
研究員
要約
1 研究の目的
所得税が課税の対象としている種々の経済取引ないし経済活動は、原則として当事者間における自由な意思決定に基づいて形成される。そして、その結果生ずる経済的利得を基礎として所得税の課税所得が算定され、一定期間経過することによってその租税債権は成立する。
私的自治が支配する私法においては、このような経済的利得の基礎となる法律関係を、原則としてそれに関与する当事者の合意で有効に成立させることとしているが、例外的に、第三者の一方的意思表示のみによって、いったん有効に成立した法律関係を変動し得ることを認めている。我が国の相続法は、かかる例外的なシステムとして相続の場合に被相続人が相続人のために相続財産の一定部分(遺留分)を保障する遺留分制度を規定している。すなわち、被相続人が行った財産の無償処分(遺贈等)に対して、遺留分を請求できる相続人(以下、「遺留分権利者」という。)は、その一方的意思表示により、じ後的にその財産の一部を取り戻す(減殺請求)ことが法的に保障されているのである(民1028、1031)。
では、例外的に設けられた遺留分制度は、課税上の局面においてどのような問題を生じさせるのであろうか。例えば、遺贈により取得した貸付用不動産から生ずる不動産所得の申告を行っていた受遺者が、遺留分権利者より減殺請求を受け、当該不動産を返還した場合、受遺者及び遺留分権利者に係る課税関係はどのようになるのか。換言すれば、減殺請求の対象財産から生ずる所得は、誰に、いつの年分に帰属するのかという課税上の問題が惹起されることとなる。特にこのような課税関係は、遺産分割に伴う調停・判決等を経ることが多いことから、相続人間の権利関係が確定されるまでの期間は長期に及ぶこととなり、このことが問題を複雑にしているのである。
そこで、本研究を通じて、私法上の遺留分減殺請求権に係る遺留分権利者と受贈者又は受遺者等(以下、「遺留分侵害者」という。)との法律関係を踏まえ、遺留分減殺請求時からその権利確定時までの期間における課税時期及び所得の帰属について検討する。更に、遺留分減殺請求により権利関係が変動することとなる相続財産から生ずる所得に係る課税関係の是正についても併せて検討を加える。
貴重な資料も含め参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月23日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。