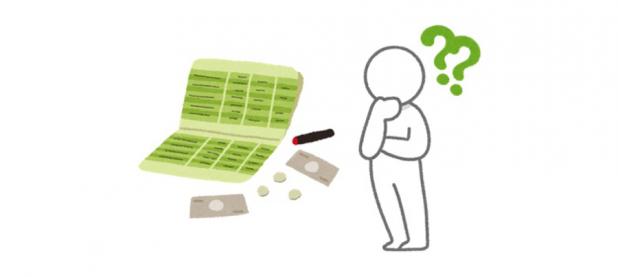夫の親の不動産相続、妻か夫か?相続後の節税効果は?
夫の母親が、住居6棟事務所2棟の、350万ほどの家賃収入のある不動産を1軒持っています。
夫の父は数年前に他界し、今は土地建物共に87歳の母の名義になっており、夫は一人っ子で兄弟はおりません。ちなみに、建物は昭和51年に建てたものです。
ゆくゆくの相続後のことですが、今から遺言書を準備して妻が相続するか、そのまま夫が相続するかどちらがどちらが節税効果が高いでしょうか?
夫は600万強の年収があり、私は専業主婦のため収入はありません。私が相続者となると、収入の金額から扶養家族から抜けることになり、国民健康保険と年金などをを支払う義務が出てくるはずです。
また、人気の地区だからか、不動産を売って欲しいという問い合わせも度々あります。
今後のことを考えて、今からできる対策はありますか?
税理士の回答
一親等の血族及び配偶者以外の方が、相続又は遺贈により財産を取得する際の相続税については2割加算しなければなりません。
したがって、ご相談者様が、お義母様から遺言で財産を取得する場合は、上記に該当し、ご主人が相続で取得するより、2割相続税が多くなってしまいますので、注意が必要です。
また、相続対策しては、従前から言われていることですが、ご家族に対して生前贈与することにより財産を減らすことが考えられます。

こんにちは。
もしご質問者様が義理のお母様から財産を相続されることをお考えの場合、養子縁組を行って法定相続人になることができれば、相続税の基礎控除額が600万円増えますし、相続税の2割加算の対象にもなりませんので大きな節税メリットがあります。
また、ご主人に600万円強の給与収入がある一方、奥様が専業主婦ということであれば、不動産収入を奥様が得るようにして所得を分散させることで所得税・住民税の節税効果も得られます。
もちろん、扶養から外れることでご主人の税金が上がったり、奥様の社会保険料負担が生じるというデメリットもありますが、所得分散による節税メリットを打ち消すほどのものではないと思われますので、一定の効果は期待できます。
その他、
・不動産管理法人を設立し、賃貸物件のうち建物だけを法人に移転させ、不動産収入を給与として分散させる(生前でも可能)
・建物を生前に贈与する(暦年贈与or相続時精算課税贈与)
といった手法も考えられますが、どのような方法が最適かは、お母様の所有されている財産の状況、かかるであろう相続税の見込額にもよりますので一概には申し上げられません。
まずは一度、お母様の相続税を試算されてから、具体的な方策を検討されることをお勧めいたします。
先日はお二人からのご返答、ありがとうございました。
とても参考になります。
固定資産税課税明細書から確認しますと、宅地建物合わせて1400万ほどです。預貯金は、孫2人と息子の口座に年100万ほどづつ移しているため、さほどありません。
そういった場合はどうでしょうか?

こんにちは。
お話を伺う限りでは、今すぐに大々的な相続税対策を行わなければならない状況ではないように思われます。
ただし、将来的には奥様が物件を持たれたほうが所得税対策になりますので、まずはとりあえず養子縁組だけでもされた方がよろしいかと思います。
相続人以外が遺言で財産を取得した場合、相続人が遺産分割協議又は遺言で財産を取得した場合に比べて、
・相続税が2割加算される
・不動産の登記費用(登録免許税)が5倍になる
・不動産取得税がかかる(相続人はかからない)
といったデメリットがあります。
ご返答、ありがとうございます。
なんどもお伺いして申し訳ないのですが、養子縁組について教えて下さい。
養子縁組を調べてみると、特別養子縁組と普通養子縁組があるようですが、裁判所に委ねるとしてあります。
また、この場合の養子縁組とはどちらを指すのでしょうか?
正直、特別養子縁組だと少し抵抗があります。

こんにちは。
通常は普通養子縁組を行います。
役所に書類を提出するだけで、手続きはそれほど難しくありません。
ありがとうございます。
そうすると、今後の固定資産税と収入の確定申告について考えてしまいます。
普通養子縁組をし、私と主人で相続権を持つとします。
権利が2人になる所ですが、所有者は私1人にして私が全て権利を持つようが良いでしょうか?
土地と建物で主人と分散する方が良いのでしょうか?
評価値で言うと、土地が1千万ほど、建物が450万弱です。
ちなみに30年度は固定資産税85000円、都市計画税23000円でした。
固定資産税と家賃収入の所得税、どうなりますか?
お忙しい中いろいろとお答えいただき、申し訳ありません。
とてもわかりやすいので、つい甘えてしまいます。
ありがとうございます。

こんにちは。
基本的には、ご主人と奥様の収入(給与・年金・不動産)がなるべくどちらかに偏らないようにできれば一番節税になります。
ただし相続はいつ発生するかわかりませんので、ご相続時点以降の収入見込に応じて物件を相続する方を決めればよろしいかと存じます。
例えば、ご相続時点ですでにご主人が退職され年金収入のみになっている場合には、奥様単独で相続せずご主人の名義も何割か入れる(物件を共有にする)といった方法も考えられます。
ありがとうございます。
主人が48、私が45歳です。
アパートは鉄筋で築年数が40年ほど経過しています。
さほど先は持たないと考えていますが・・・
私は主人会社の厚生年金に加入していますが、国民年金に加入となると将来の年金が気になるところです。
そこを考えても、今扶養から抜けて私の収入とし、国民年金を満額支払うとしても税金対策、将来的にもメリットがあるといいう事でしょうか。
なんども同じ事を聞いているかもしれません。
申し訳ありません。
お忙しい中のご返答、感謝しております。

こんにちは。
現在ご質問者様はご主人の扶養に入られているため国民年金の第3号被保険者という扱いとなっており、これが扶養から外れると第1号被保険者になるわけですが、将来の受給額については(1号になった場合に保険料をきちんと納める限りは)どちらも変わりません。
厚生年金をもらえるのはあくまで本人だけで、扶養に入っている配偶者は国民年金しかもらえません。
したがって、ご主人が不動産所得を得た場合の税負担の増加額と、ご質問者様が不動産所得を得た場合の税負担・社会保険料負担の増加額を比較して、どちらが相続するかを選ばれたら良いかと思います。
ただし同じ話で恐縮ですが、あくまでご相続があった時点の状況から判断することになります。
ご返答ありがとうございます。
そこが一番大きな所ですね。
そういった増価額を比較するためには、私では計算が難しいように思います。
やはり税理士さんに計算をお願いするのが一番という事なのでしょうかね。
詳しくご説明いただき、また忙しい時間を長く割いていただき、感謝しております。
ありがとうございました!
本投稿は、2018年09月10日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。