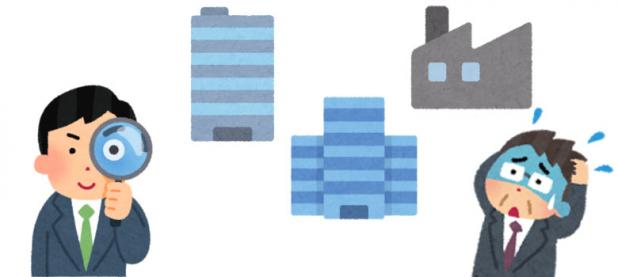国税徴収法142条について
国税徴収法に基づく捜索には令状不要である(憲法35条が類推適用されない)理由と犯罪捜査を目的とする刑訴法に基づく捜索と比較してどちらが権限が強いか理由を教えてください
税理士の回答
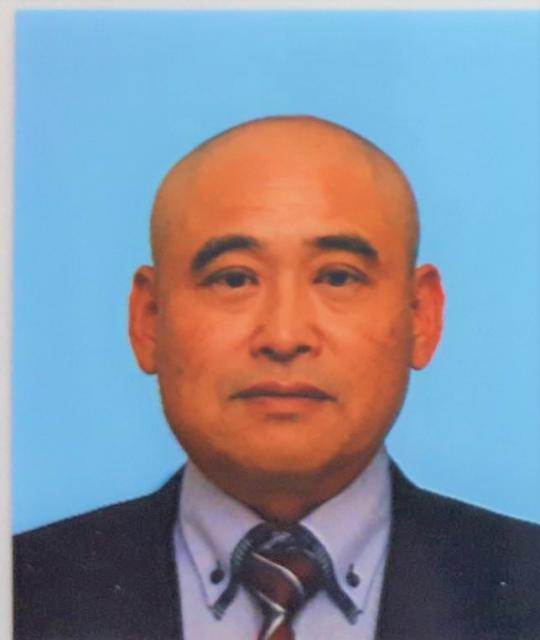
国税徴収法142条の捜索は犯罪捜査を目的としておりません。よって、令状が不要となっているものです。捜索の権限の比較ですが、目的が犯罪捜査と財産調査ということで異なるので比較が難しいと思います。
捜索の権限の比較ですが、目的が犯罪捜査と財産調査ということで異なるので比較が難しいと思います。
わかりました。では、強制力はどちらが強いですか?
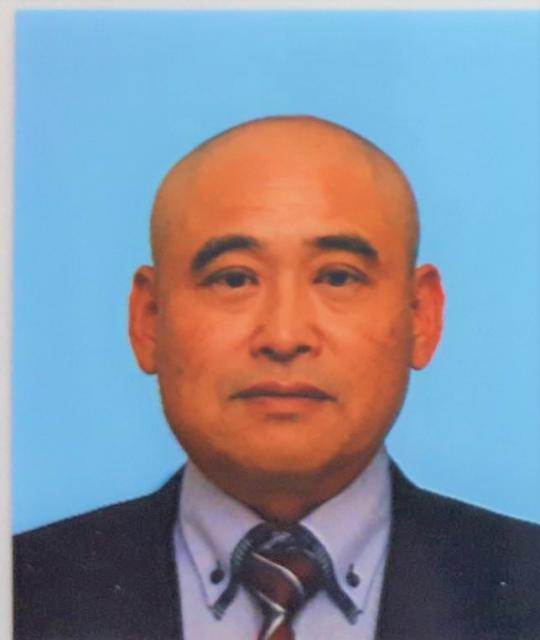
目的はそれぞれ異なりますが、捜索手続きは同じです。ですから、強制力としては同じだと思います。ただ、捜索を実施するにあたり、国税徴収法の捜索の場合は「国税徴収官の裁量」によるものが多いです。一方、犯罪捜査を目的とする捜索の場合は令状が発行され、当該令状に「捜索する場所・物等」を特定することとなります。
ありがとうございます。でも、私は国税徴収法より刑訴法の方が強い権限があると思います。以下、根拠を列挙します。
閉鎖してある戸・扉・金庫等の開扉(142条3項)については、徴収職員が自ら開くのは、滞納者等が徴収職員の開扉の求めに応じないとき、不在のとき等やむを得ないときに限るとされ(国税徴収法142条関係基本通達7)、錠の除去に当たって、器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮するとされている(同基本通達8)。これに対して、犯罪捜査を目的とする刑事訴訟法の捜索については、そのような配慮がなされることはなく、被疑者が開扉しない場合、エンジンカッターなどを用いて開扉することも可能である。
捜索中に禁制物(麻薬・覚醒剤・拳銃等)が発見された場合、国税徴収法による捜索の場合、動産として差し押さえることができないが、刑事訴訟法による捜索の場合、禁制物の差押も被疑者の逮捕も可能である。
捜索に際して、滞納者が激しく抵抗する可能性があったとしても、国税徴収職員には拳銃の携行が認められていないが、司法警察員には拳銃の携行が認められている。
また、司法警察員による捜索では、身体検査令状の発付を受ければ、身体検査が可能である(刑事訴訟法218条1項)が、国税徴収職員による捜索は、「滞納者の物又は住居その他の場所」(国税徴収法142条1項)、特別な場合には「第三者の物又は住居その他の場所」(同条2項)を対象にして行われ、身体検査を行うことはできない。
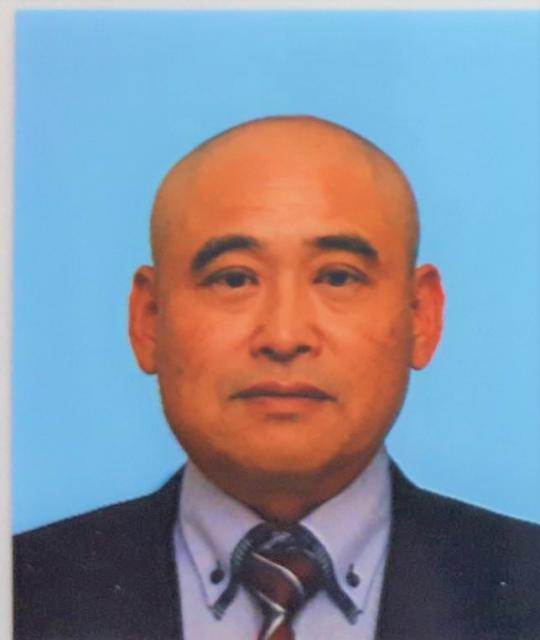
すばらしい回答だと思います。頑張ってください。
本投稿は、2019年12月22日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。