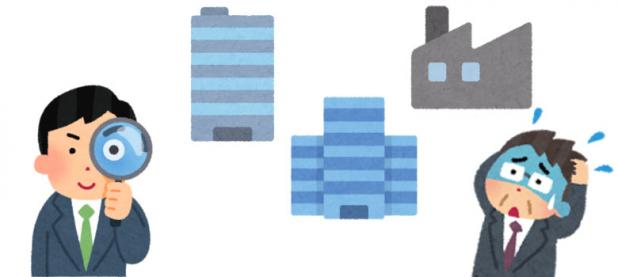同じような業務を営む2社間の取引について
業務コンサルティング・アウトソーシングを営む株式会社Aを運営していましたが、諸事情によりもう1社株式会社Bを設立しました。(私はA社とB社の両方の代表取締役です)
既に以下の通りで運用していますが、いまさらながらこれは問題なかったのだろうか?と思い質問させていただきます。
・A社の社員(アルバイトのみ)は移管や出向などはせずそのままA社の雇用としています。A社の取引先はB社のみとし、業務委託契約でB社の業務を代行しています。(A社は営業活動をすることはありません)
・B社は社員なし、社長ひとりのみで、主に社長の営業活動によって仕事を獲得しています。
・B社で獲得した業務委託の仕事は、A社に業務委託しアルバイトが作業、もしくは、B社が他の外注さんに業務委託して作業しています。
この取引を始めるにあたり2社間で業務委託契約書を作成し、秘密保持契約書も作成しました。
また、A社からB社に対する毎月の請求は、A社で私とアルバイトが作業した時間×単価(標準的な単価です)という基準を決めて請求書を発行しています。
経費は、営業にかかるものはB社で(例えば営業のための交通費)、委託された業務を遂行するのに必要なものはA社で、と振り分けています。
ちなみに、2社目設立の理由は、節税などではありません。
第三者によるA社に対する営業妨害が予測される状況があったので、別法人B社を設立し、顧客には事情を説明してB社と取引に移行してもらいました。
このような状況です。
先生方のご意見を頂けますと幸いです。
税理士の回答

A社からB社に対する毎月の請求は、A社で私とアルバイトが作業した時間×単価(標準的な単価です)という基準を決めて請求書を発行しています。
①A社も、B社も、代表取締役ですから、私の分は、請求できません。
アルバイトの分は、正確な計算方法なら、良しと、考えます。
②税務調査の際には、しっかりと、記載された内容を説明しぬいてください。
よろしくお願いします。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
文章のニュアンスから「あまりよくない処理をしている」と感じるのですが、やはりこのやり方は税務調査などでは認められにくいものなのでしょうか?
また、こちらのサイトで以下の質問を見つけました。
税理士さんの回答では、問題なしとのようです。
>企業の代表取締役業務を個人会社に業務委託することは可能ですか?
>米国ベンチャー企業の100%子会社として今年日本に設立された会社の代取CEOです。他にも非常勤役員を何社か勤めておりそれらの会社とはそれらの会社と私の個人会社との間で業務委託契約を締結し、役員報酬としてではなく業務委託契約料として個人の会社に支払っていただいています。今回のような代取CEOの場合その業務を私の個人会社との間で業務委託契約として結び役員報酬ではなく、業務委託料として受け取ることは所得税法上許されるしょうか?会社法の対応は既に出来ております。ご意見を頂戴できれば幸甚です。
これがOKであれば、私の場合、今後はA社とB社の業務請負契約を、B社の代表取締役業務の業務委託契約にしてもよいのでしょうか?
またその場合、A社で業務を行ったボリュームに対して、毎月の委託料も増減しても問題ありませんか?
ちなみに、B社では役員報酬を得ていません。
恐れ入りますが、よろしくお願いします。

会社間の取引については、むつかしい判断ですが、ケイスバイケースでしょう。
代表取締役個人との取引は、認められにくいです。
役員報酬とされると思います。
よろしくお願いします。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。

参考にしてください。
竹中が、税理士として心がけること
①会社の経理処理が、税務調査に耐えうるかどうか?
これは、常に顧問先の社長・経理担当者と、話し合います。・・・でも、先方はそう思っていなおかもしれません(*_*;???
(税務調査のみを気にするだけでなく、税務調査官に指摘されたときに、法的に闘えるかどうか・・・?)
②変だなあ?これでいいかなあ?・・・については、話し合います。
③実行する前に話してください・・・とも言います。(なかなか、そうはいきませんが・・・)
相談者様の、事前のこのような調べは、本当に頭が下がります。
④当然ということにも、落とし穴があります。例でいえば、無償の譲渡に、贈与税や所得税がかかるなど・・・。
⑤法人の行為には、常に経済的な側面で、考える必要があります。経済的な行為=絶えず利益の追求という立場て、考える必要があります。
そうでない場合には、法的に大丈夫かと、=寄付金などの例。定期同額給与と事前届出給与など・・・。
慎重になりながら、大胆に、頑張ってください。
期待しています。
本投稿は、2020年05月10日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。