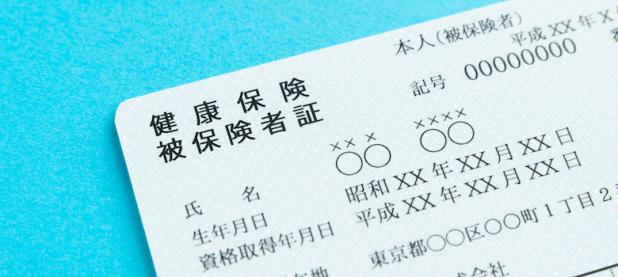新サービスの検証にかかった費用の処理科目
お世話になっております。既存サービスで得たデータを活用して新たなサービスのアイディアを社内で検討していますが、発売前にモニタリングにかかった費用は、研究開発費の実務指針に記載されている要件に当てはまるのでしょうか?
これには製品・ソフトウェアの新製品のような”開発”といった行為は一切ないため、研究開発費で処理することに違和感を感じています。
例えば、テレビ制作者が探しているモニターの条件に当てはまる視聴者を、弊社アプリの視聴データから探し出して紹介する(弊社はテレビ制作会社から手数料をもらう)という今までになかったサービスを考え、これが本当に商売として成り立つのか無料で試してもらいます。
税理士の回答

「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」は、「研究開発費に係る会計基準」を踏まえて、以下のように規定しています。
「研究・開発の範囲
2.「研究開発費等に係る会計基準」では、研究とは、「新しい知識の発見を目的とした計
画的な調査及び探究」であり、開発とは、「新しい製品・サービス・生産方法(以下、「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること」とされているが、これら研究・開発の典型例としては以下のものを挙げることができる。
① 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究
② 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化、業務化等を行うための活動
③ 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
④ 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化
⑤ 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
⑥ 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化
⑦ 新製品の試作品の設計・製作及び実験
⑧ 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
⑨ 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動」
個人的見解ですが、文面を読む限りでは、上記の費用は、今までになかったサービスを考え、これが本当に商売として成り立つか試してもらうための費用とのことなので、実務指針の典型例の①②にあてはまると考えられます。
したがって、上記費用は、研究開発費の定義に該当し、研究開発費として処理して差し支えないものと考えられます。
唐澤先生、回答ありがとうございました。
開発行為そのものが無くても、従来にないサービスの調査・探究に当てはまれば研究開発費として処理できるということで安心しました。
本投稿は、2021年06月10日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。