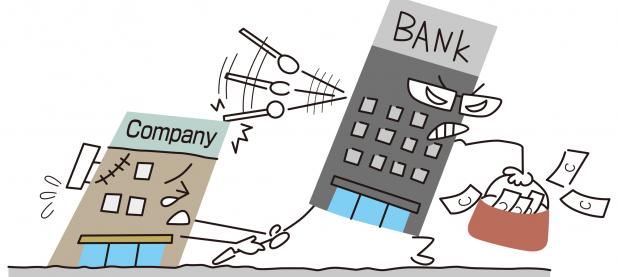法人設立1期目の決算・確定申告・納税の際の必要な書類(売上0/経費少しあり/遅延中)
前回同じ質問をしたところ、納得のいく回答がなかったため、再度質問させていただいております。
(※「税理士に依頼してください」と流したり、具体的に答えられない方の回答はお控えください。)
2020年4月30日に法人を設立しました。
(資本金は1000万円未満)
今年2021年3月末決算なのですが、コロナ等の事情で事業が全く回らず、少しの経費(15万円程度)はかかっているものの、売上0という結果に終わってしまい、お金のやりくりができず2021年8月現在まで決算・確定申告と納税ができていない状態です。
休業届は提出しておりません。
この際の「決算」・「確定申告」・「納税」の際に具体的に必要な書類をご教授いただけますと幸いです。
また可能であれば、遅延金含め総額どれくらいの金額を納税する必要があるのか、おおよそでもご教授いただけると助かります。
会計ソフトは「弥生会計」を一応契約しています。
勉強不足で無知な点ご容赦ください。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
それでは、ご質問にそのまま回答します。
この際の「決算」・「確定申告」・「納税」の際に具体的に必要な書類をご教授いただけますと幸いです。
「決算」
貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、株主資本等変動計算書、個別注記表、総勘定元帳
「確定申告」
法人税・地方法人税
必須のもの・・別表1、別表2、別表4、別表5(1)、別表5(2)、勘定科目内訳書、法人事業概況説明書
内容に応じて添付するもの・・別表1次葉、別表6(1)、別表7(1)、別表8(1)、別表15、別表16(1)~(8)(文面からの想定なので必要ないものもあり得る)
都道府県民税
必須のもの・・第6号様式
内容に応じて添付するもの・・第6号様式別表9
市町村民税
必須のもの・・第20号様式
「納税」
法人都道府県民税の納付書と法人市町村民税の納付書
また可能であれば、遅延金含め総額どれくらいの金額を納税する必要があるのか、おおよそでもご教授いただけると助かります。
都道府県民税均等割額(以下の①と②の合計)
①11か月分・18,300円~22,000円(自治体によって異なる)
②延滞金 ①×1%×30日/365日と①×8.8%×5月1日~納付日までの日数/365日の合計
市町村民税均等割額(以下の①と②の合計)
①11か月分・45,800円~55,000円(自治体によって異なる)
②延滞金の計算式は都道府県民税均等割額と同じ
延滞金の計算を訂正します。
②延滞金 ①×2.5%×30日/365日と①×8.8%×5月1日~納付日までの日数/365日の合計
ご親切丁寧にありがとうございました。
非常に助かりました。

説明をさせていただきます。
「必要な書類」と「延滞税」などの計算方法は、前田先生のご回答となりますが、初めての決算のため、社長様は用語になじみがないのかと存じます。少しでもお役に立てましたらと思い説明をさせていただきます。
なお、新しく同じ質問をされていますので、他の先生が回答される機会を考え、こちらから説明させていただくことをお許しください。
以後の説明でご理解をすこしでいただければ助かります。
【決算書】
「決算書」は、会社の1年間の経理の結果となります。
税務署で法人税の申告書の作成相談をする際にも『「決算書」は会社で作るものなので、その決算書を持ってきてください。と言われます。』
なお、御社では弥生会計をご利用されているとのお話ですので、弥生会計から「決算書」は作成・・・印刷までできます。
弥生会計の、画面の右上に「ナビゲーター」というものがありますので、そちらの画面から少し説明します。
・導入(一番左の画面)・・・会社の情報、科目などの設定を行います
・取引・・・毎日の取引(経費などの支払い)の仕訳をします
・集計・・・試算表などを作成し、日次・月次の経営結果を確認できます。
・決算・申告・・・・決算書作成
弥生会計も契約しているソフトによって画面や入力するシステム(?)が違うようですので、詳細が間違っていたら申し訳ございません。
ただし、いずれの場合も毎日の取引を入力していくと「決算書」までの作成ができるようになっています。
例えば
法人設立時
現金 100万円 /資本金 100万円 でスタートし
経費だけが掛かったとの説明ですので(仕入なし)
例えば
消耗品費で5万円
交際費で2万円
交通費で1万円 の必要経費の支払いがあった時には
貸借対照表
(借方) (貸方)
現金 92万円 / 資本金 100万円
繰越利益剰余金 △ 8万円
損益計算表
(借方) (貸方)
消耗品費 5万円/ 当期純損失 8万円
接待交際費 1万円/
旅費交通費 2万円/
※決算書の形式は様々ありますので、簡易な書き方をしています。なお、翌期に支払う「法人事業税」などを計上しない形で「当期純損失」としています。
【法人税申告書】
申告書の用紙は、税務署から送られてきていませんか。
御社が青色申告法人の場合は、赤字(欠損)の場合は、翌期以降の黒字と相殺できますので、「別表7」 という様式が必要になります。この様式は送られてきていませんので税務署で入手してください。
作成方法は、別四 ⇒ 別五 ⇒ 別十五⇒ 別四 ⇒ 別一と別七 ⇒別一 などと別表と言われる様式を行ったり来たりして、所得金額を算出・作成するのですが、簡単に説明します。
長くなったので続きます。

続きです
[別表四]
別表四は、税務上の「損益計算書」と言われています。
まずは、一番上の「当期利益又は当期欠損の額」に△8万円と記載します。
次に、加算・減算をした上で一番下の欄「所得金額又は欠損金額」を算出しますが、今回の例では加算・減算項目はありませんので、割愛します。
別表四で計算した欠損金額(△8万円)を、別表一の「1 所得金額又は欠損金額」に転記します。
[別表五(一)]
別表五(一)は税務上の貸借対照表と言われています。
上部の表「Ⅰ利益積立金の計算に関する計算書」は、第1期ですので期首の記載はありません。
当期の増減の増と差引翌期首・・の 「繰越損益金」に△8万円を記載します。
その下の「未納法人税等」のうち、未納道府県民税・未納市町村民税は、地方税の計算をした金額を記載します。
今回は「均等割り」のみ記載されます。
下の表「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する計算書」は
期首現在及び差引・・・の欄に100万円を記載します。
[別五(二)」
当期中に支払ったり発生した税金などの租税公課の明細を記載します。租税公課には、損金(税務上の経費)になるものとならないものがあり、損金にならない支出等は、別表四で加算します。
今期は、地方税の均等割り分が、「当期発生税額」の当期分・確定に記載されます。
[別表十五]
交際費の損金算入に関する計算をします。
今回の例ですと、全額損金になりますので、「科目」に接待交際費、6と8に2万円と記載し、そのまま上部の計算式にあてはめます。
[別表七」
青色申告法人の場合は、欠損金は翌期以降に繰り越されます。
当期分の「欠損金額」に8万円を記載し、別表一の「32 翌期へ繰越す欠損金」に8万円と記載します(マイナスは付けない)
この他、固定資産(減価償却資産)を購入した場合等は、別表十六なども作成しますが、割愛します。
会社の決算内容によって別表類も変わりますので、ここでご紹介できものには限りがあり、申し訳ございません。
内訳明細書は該当するものを作成しますが、全ての作成が大変なようでしたら、「預貯金の内訳書」など作成できるものだけ作成すればよろしいのかと思います。

地方税の申告についても説明したと思っていましたが、投稿されていませんでした。申し訳ございません。
投稿できる文字数に限りがあり、分かれての説明となっております。
なお、法人の登記住所や支店数などによっても、若干申告が異なりますが、基本的な説明とになること、お許しください。
また、申告書の様式や納付書が送られてきているかご確認ください。送られてきていない場合は、それぞれの窓口(都道府県税事務所・市区町村の課税課など)でご入手ください。
【都道府県民税】
[第六号様式]
様式の左上の欄は「事業税」の計算カ所になります。
一番上の「所得金額総額」欄には、△8万円をご記入ください。
様式の左下は「特別事業税」の計算カ所になります。
同じように所得金額を記載することになりますので、△8万円をご記入ください。
そのまま仮計と一つ開けた「法人税の所得金額」欄にも△8万円をご記入ください。
様式の右側は「道府県民税」の計算を記載します。
今回は「均等割り」だけの計算になりますので、真ん中位の箇所に月数として「11」を記入し
20,000円×11/12=18,333円 ∴ 18,300円の税額になります。
※ 4月20日設立 3月末日決算のため、一月に満たない月数は減らします。
[第六号様式別表九]
「法人税の別表七」同様に、青色申告法人の場合は欠損金を繰り越しますので、この様式に「当期分 欠損金額等(〇付) 8万円を記載します。(マイナスは付けません)
【法人住民税】
「第二十号様式]
様式の中心より少し下に、「均等割り」の計算する箇所があります。
「道府県民税」と同様に、月数を「11」と記載します
50,000円 × 11/12=45,833円 ∴45800円の税額になります。
地方税の計算が終わりましたら、法人税の申告書の「別表五(一)」及び「別表五(二)」の、地方税額を記載します。
その他、法人税・地方税の申告書とも、決算確定の日(決算書を作成し、株主総会で承認を受けた日)、資本金等の金額も記載します。
※ 御社の登記された地域が「東京都 特別区」の場合は、均等割り額7万円で、都税事務所への申告のみとなります。
地方税は、地域によって多少取扱いが異なりますので、念のため、それぞれの担当部署に確認されることをお勧めいたします。
また、申告書が送られてきている場合は、注意点や提出場所などの案内等が同封されていると思われますので、ご確認ください。
よろしくお願いいたします。
ご親切丁寧に誠にありがとうございました。
助かりました。本当にありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
一つ説明が抜けていました。申し訳ございません。
【法人税(地方法人税含む)の確定申告書】
提出先は、税務署(国税)になります。
申告書の綴りは大きく「3」つで構成され その他に「法人事業概況説明書」の提出が必要になります。
1 別表類
法人税等の確定申告書は、正確には「別表一」が該当します。
しかし、その他の別表は、法人税額などを計算するために必要となる書類ですので、会社の経理・決算内容によって提出・添付するものは異なります。
最低でも、別表一の他、四 五(一)・五(二)は必要となります。
青色申告法人で欠損の繰越がある場合は、別表七
交際費がある場合は 別表十五 が必要になります。
2 決算書
原本ではなく、写しでかまいません。
法人税等の申告は「確定した決算に基づき」となっていることと、減価償却費など「決算」で経費で計上していない費用は、損金として認めないなどの規定があるため、必ず必要となります。
3 内訳明細書
決算上の各項目(資産・負債・費用等)のうち重要なものの明細を記載することになります。
弥生会計でも作成できるようですが、私は弥生会計では作成したことがないため、注意点が分かりません。
分かる範囲で作成してください。
法人税等の確定申告書というと、上記の1~3を綴った物となります。
4 「法人概況説明書」
文言のとおり、会社の概況を記載します。
PCの使用、ソフトの種類、経理担当者など記載します。
また、決算上重要な項目の金額を記載します。
申告書には綴らず、別に提出します。
こちらも弥生会計でも作成できるようですが、私は弥生会計で作成したことがありませんので、注意点が分かりません。申し訳ございません。
【地方税の申告書】
都道府県民税・市区町村民税は、先の第六号様式などになります。決算書などの添付は必要ありません。
前田先生も決して間違った説明をされたわけではありません。
「必要な書類」としての説明でしたので書類名を紹介させていただいたものと思います。
別表類は、経理・決算内容によって添付する書類が大きく変わりますので、その点ご容赦ください。
なかなか、「文章」で説明するには、法人税の申告書は複雑であり、ご希望にお答えできない面が多々あると思いますが、どうかお許しください。
最後に1点、注意事項があります。
青色申告法人は白色申告法人に比べて「欠損金の繰越制度」などがあります。
しかし、期限後が続きますとその青色の特典が取り消される可能性がありますので、何かと大変でしょうが、来期は期限内に申告できますように、ご注意ください。
本投稿は、2021年08月26日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。