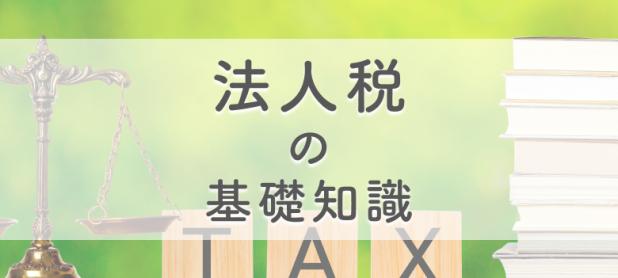使用貸借と連帯納税義務
使用貸借では固定資産税の連帯納税義務はどのような扱いになりますか?不動産は共有状況で名義は被相続人です。居住地の税務課も共有告知も積極的ではありません。共有者も負担出来ないと無視されて困っています。
税理士の回答

坪井昌紀
数日間、回答がないようですから、簡易回答だけしておきます。
結論は、固定資産税の課税庁である市役所とよく話し合ってくださいという事になると思います。
一般的なケースであれば、親族であるAとBが共有所有の土地について、Aが共有部分の賃料をタダでBから借りているような使用貸借のときは、維持管理費としての固定資産税をAが全額負担するというのは、よくあります。
遺産分割協議の際に後先考えずに分割のみを優先した場合は、固定資産税の支払いで不都合が生じることがありますが、貴殿はこれに類似したケースと推測されます。
固定資産税は、どの市町村でも代表者1人に全所有権分の税金を通知することにより賦課しています。
さて、貴殿のケースは被相続人が負担することとなっていた固定資産税を今度は、誰が納税義務者として継承するのかということですが、通知が被相続人宛に届いている分はもちろん相続人で対処する必要があります。
この際には、共有者ごとに負担率で他の所有者に請求することは必要です。相続税の計算上は、所有権分の債務しか控除にならないような計算になるからです。
一方、相続発生の翌年の固定資産税は、誰を通知先にするのかという事が貴殿の本題だと思います。
一般的には、単独所有で単独相続人である場合は、相続登記変更後にその登記を市役所が独自に確認して、次の相続人へ通知する流れになります。
しかし、共有不動産の所有者である固定資産税通知を受けていた1人が亡くなった場合における通知先は、相続登記するまでの間、誰を通知先とすべきかの問題を言っているのだと思います。
共有の場合などは、固定資産税を誰にするのかの届出書があり、これをもって、その1人の者へ通知しているので、変更したい場合は、その届出を変更する必要がありますが、今回は、相続が関係しています。
問題解決には至りませんが、事務の現状と貴殿の状況整理をしたうえで、市役所に相談、そして、他の相続人への負担交渉をしていくしかないと考えられます。
共有物件については、一方の買取や贈与、全員での売却が最終手段になることが多くあります。
土地が広いケースでは、所有権割合で面積を測量分割して土地を2分し、共有物分割登記して単独所有とする手法もあります。こうすると、それぞれの所有者に固定資産税は通知されます。
あくまで、簡易回答ですから、ここまでとしておきます。
有り難うございます。早速役所にも相談してみます。
本投稿は、2025年06月25日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。