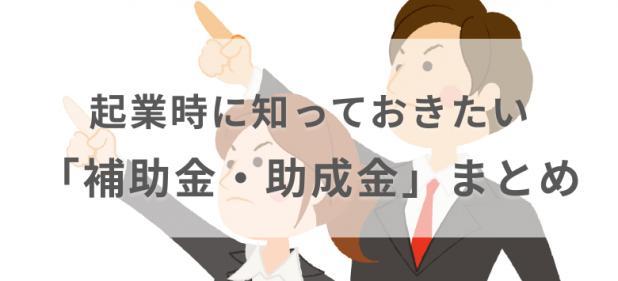持続化給付金について
持続化給付金について質問いたします。
現在、
事務所(会社)と業務委託契約契約を結んでいて、事業所得があります。
確定申告は白色申告(事業所得)です。(開業届けは出していない)
来月の収入がゼロになることが確定したため(去年度の月平均所得と比べ50%以上の減収確定)
来月を当該月として給付金申請をしようと考えています。
上記が現状なのですが、
収入の足しにしようと、
6/1~7/14まで、新たにアルバイト(一ヶ月半くらいの派遣短期契約、その期間は派遣会社の雇用保険加入必須)をしたいと考えています。
この場合は、給付金受給対象を維持できますか?
税理士の回答

そのアルバイトについては給与所得となると思いますので
今回の給付金の判定の際には関係なく、対象のままだと思われます
ただ、給付金の条件として、事業を継続する意思があるというものがありますのでその後も事業を続ける必要は出てきます(売上が上がるかどうかは別として)
ご返答ありがとうございます。
もちろん事業継続意思あります
それとすみません、先ほど、記載忘れたのですが
去年度途中から夫の扶養内に入り、扶養内で事業所得を得ているのですが
それも特に、問題ないですか?

扶養内であっても可能です
ただし、この持続化給付金は貰った場合に売上と同じく税金がかかる売上となります
ですので仮に50万円給付金をもらった場合にはその分売上が上がったことと同じになるので
それによっては扶養の条件から外れてしまう可能性もあります
前年度売上105万
今年4月売上ゼロ
105÷12=8.75
8.75×12=105
上限は100万ゆえに
給付金100万受給、仮にこれが7月に入金されたとしたら、7月の収入が100万(+予定しているアルバイト収入)ということにはなり、経費などはないため、
そのまま100万+αが普段の所得に+で所得として計上されるということですか?
だとしたら
もはや、年間130万は越えてしまうため(夫の健康保険団体は、経費差し引きを認めていないため今は、収入130万以内で働いています)税金の扶養は外れるのはもう仕方ないとして
社会保険の扶養はどうなるでしょうか?
ただ1ヶ月10.8万円を越えた収入を得ることになりますが、翌月からまた収入が普段通り(10.8万以内)になっても、一年間(今年度)の合計が130万円をこえてしまうとなると扶養から外れてしまいますか?
そのタイミングはいつですか?

社会保険については専門外のためお答えができないのですが
所得税の場合ですと、配偶者の場合には所得が48万円を超えたとしても133万円までであれば金額は少なくなりますが配偶者特別控除を受けることができます
ありがとうございます。
給付で100万所得を得てしまったらもう今の時点で133万越えてしまいます、、。
ちなみにですが
夫、年収約650万です。仮に扶養を外れたてしましたら、所得105万の前年と比べましてだいたいどれくらい税金がプラスされますでしょうか?
給付金もらって扶養を外れるるのと、もらわず、扶養にとどまるのとどちらがいいのか、考えようと思います。
何回質問しまして申し訳ありません
補足
去年度は、わたしの所得は105万であったため、配偶者特別控除が、適応されました

所得105万円の時の配偶者特別控除の額は21万円(これは去年までの金額です)です
なので仮に今年の所得が133万円を超えるようですと、旦那さんはこの控除を受けることができなくなります
その影響ですが
所得税の場合には年収が650万とのことですので、他の所得控除(社会保険料控除やこどもさんの扶養控除など)の状況がわかりませんので
一般的な税率ですと20%になりますので
所得控除21万円が減ると
21万×20%で42,000円ほど所得税が上がると思われます
もう一つ住民税は21万所得105万円の時の配偶者特別控除の額は21万円(これは去年までの金額です)です
なので仮に今年の所得が133万円を超えるようですと、旦那さんはこの控除を受けることができなくなります
その影響ですが
所得税の場合には年収が650万とのことですので、他の所得控除(社会保険料控除やこどもさんの扶養控除など)の状況がわかりませんので
一般的な税率ですと20%になりますので
所得控除21万円が減ると
21万×20%で42,000円ほど所得税が上がると思われます
もう一つ住民税は21万×10%で21,000円ほど上がると思われます
なので合計すると63,000円ほど旦那さんの税金が増えるものと思われます
わかりやすい説明をありがとうございます。
社会保険扶養のほうとあわせて検討したいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月16日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。