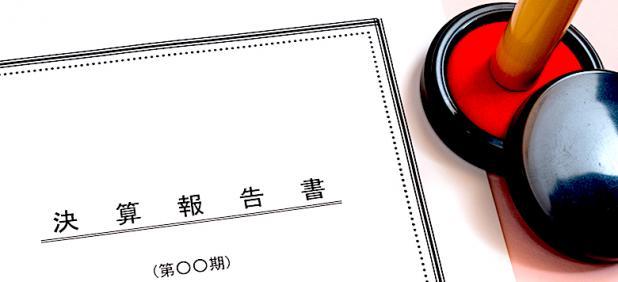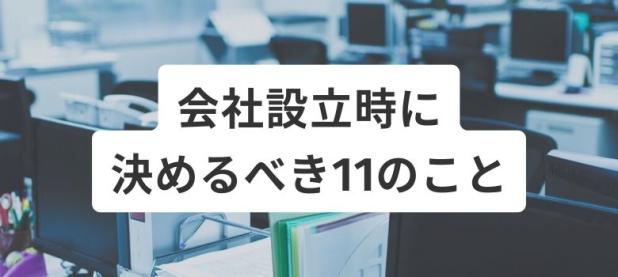セラピストで開業
セラピストの資格を取り個人事業主として開業予定です。
セラピストの資格を持ってる人を雇い、休みや仕事の時間など完全自由シフトにする予定です。
これは業務委託で大丈夫でしょうか?
またそのセラピストの報酬はその日のセラピストの売り上げの一部を渡し、残りはこちらが回収という形にする予定です。
交通費や業務で使うオイル等をこちらで負担する場合、報酬も加味して給与所得として払うのか事業所得になるのか教えてください
税理士の回答

総合勘案して判定する以上、絶対に、こうだとは言い切れない部分があります。下記にリンクを貼っておきますので、大工等をセラピストに置き換えてより否認されない方に方向をとられればと思います。
外部リンク先 国税庁HP「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
材料費というか業務で使うタオルやオイルなどはこちらで購入しセラピストの方に渡します。セラピストは負担無しです
事業所得と給与所得の違いに、材料や道具を委託された側が払うのか委託した側が払うのかで変わるみたいなこと書いてますが、こちらでタオルやオイルを経費として購入し、セラピストに渡したら事業所得じゃない気がするのですが、そこだけで判断はされませんか?

あくまでも、総合勘案ですので、そこだけで判断されることはないです。ただし、より安全策をとるなら、セラピストに購入してもらうほうがいいと思います。質問者さんが立替で購入し、その分をセラピストに支払ってもらうということでもいいかなと思います。
後、個人的に気になったのは売上の回収です。水商売で言うと、クラブホステスやホストは売掛の回収も自己責任でやる、一方、バイトキャバ嬢はそんなことやんないと。そういうことなどでも報酬、給与の違いは考えられるのかなと。
まぁ、総合勘案なので、全体をみてということとなります。
業務前におカネをもらうなどして対策をしようと思うので売り掛けに関しては大丈夫かと思います
安全策でセラピストに購入してもらうとして交通費もやはり負担してもらった方がよろしいのでしょうか?
またそういう負担をしてもらう場合 その人の売り上げは全部支給した方がよろしいのでしょうか?
一応、店舗構えず出張セラピストとしての開業でセラピストの一日の売り上げ、例えば【60パーセントをセラピスト 40パーセントをこちら】のような、形でも大丈夫なのでしょうか?

総合勘案ですので、より安全なほうが安全だということだけの話です。交通費についても、あくまでも判断材料の1つにしかすぎないです。なお、売上を全部セラピストに支給したら、質問者さんが儲からないじゃないですか。クラブやホスト経営者だって、売上をホステスと店側の取り分に分けてます。そこについては、何の心配ありません。
出張セラピストを開業 セラピストを業務委託でやとう 交通費やオイル等は自分で買ってもらう
売り上げは取り分わける
セラピストに、業務で使う資格を取る際もやはりセラピストの方に出してもらった方が安全ということですか?

資格取得に関する費用はセラピストに出してもらったほうが安全です。業務委託である以上、セラピストは個人事業主です。個人事業主が資格取得に関する費用を他人に出してもらうことは、まずないです。
セラピストがこちらと業務委託として連携したとして売り上げも取り分けられるし交通費やオイル等の、道具も自分で買わなきゃいけないってセラピスト側って何かメリットありますか?
例えば節税になる以外で

経費以上の売上があるなら、当然、セラピストにもメリットがあります。売上をガンガンあげて稼ぎたいと意欲が有るセラピストにとってはメリットがあります。ただし、そこまでの意欲がないセラピストは給与のほうがいいと言うと思います。実際、クラブホステスにも、同じ店の中に、報酬としてもらっているホステスと給与でもらっているバイトホステスが混在しているというところがあります。
メリットって節税ができるってことでしょうか?

意欲有るセラピストにとってのメリットは、給与ベースではなく報酬ベースでもらうほうが、一般的に、もらう金額が大きいこと。もう一つは経費が使えるということです。
ただし、バイト的な感覚のセラピストにとっては、給与のほうを望むと思います。確定申告をすることじたい嫌がるでしょう。
こちらはセラピストの売り上げの一部払って残りはこちらが回収する場合、セラピストは払われた分で、確定申告をするってことですか?
またこちらが一部回収する場合、それは店の売り上げとして勘定するのか、また違う項目勘定なのか教えてください
本投稿は、2019年09月26日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。