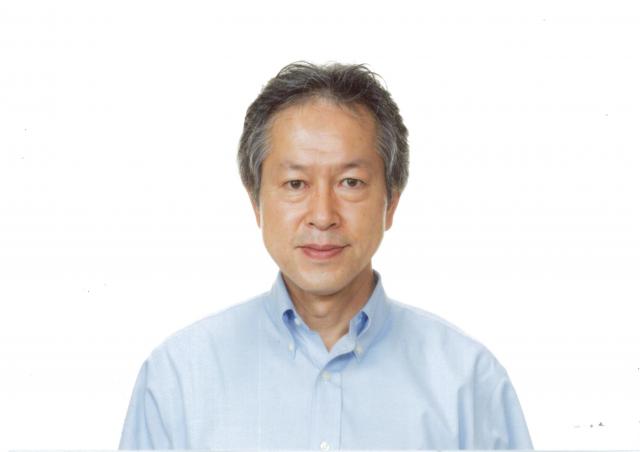住宅資金贈与に対する遺留分減殺請求の可能性について
二世帯住宅取得にあたり、住宅資金贈与の非課税枠活用を検討しています。
当該贈与額については相続財産には含まれないと勉強しましたが、他の法定相続人から、遺留分減殺請求等によって異議が起こる可能性は全くないのでしょうか。
また、少しテーマがずれますが、贈与以外の親世帯の自己資金を入れてもらう場合、比較的減価の大きい建物の持分に充当すると、土地の持分に充当した時に比べて他の法定相続人が不利になるように思われますが、相続時に問題となる可能性はありますでしょうか。
税理士の回答
民法には「特別受益」という考え方があります。
「特別受益」とは、相続人が被相続人からの住宅取得資金の生前贈与を受けた場合など特別に被相続人から受けた利益をいます。
特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると、不公平な相続になってしまいますので、このような不公平な状態を是正するため民法903条で特別受益がある場合の相続分の計算が規定されています。遺留分減殺請求の場合も生前贈与分を合計した金額を基礎として計算します。
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
上記のように贈与を受けた金額を相続財産に加算して、遺産分割をするのであれば、取得後の値上がりや価値の減少は影響しないことになりますのでおっしゃるような他の相続人が不利になるような分割にはなりません。
特別受益分を考慮しないで遺産分割をしたり、減価した財産価値を基礎に分割をしたりすると争いのもとになりかねませんのでご注意なさった方がよろしいですね。
丁寧なご回答ありがとうございます。よく理解できました。
本投稿は、2018年10月09日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。