輸入販売での棚卸し時の仕入原価の求め方
中国からの輸入で
A商品44元×2個、B商品45元×2個を
当時1元=17.15円で
【A商品】44×2×17.15=1509.2→四捨五入で1509円
【B商品】45×2×17.15=1543.5→四捨五入で1544円
商品代金合計3053円を仕入れたとします。
代行業者を通じて仕入れたため商品代金の他に、
下記の代行手数料等も支払っており、すべて「仕入高」で計上しております。
(尚、消費税の免税事業者です)
あくまでも例として、
商品代金 3053円
代行手数料 100円
オプション 100円
その他 100円
国内送料 100円
国際送料 100円
関税 100円
消費税・地方消費税 100円
通関料 100円
とすると合計3853円の仕入高となります。
①
棚卸しの際に在庫となった各商品の仕入原価を求める必要があると思うのですが、
A商品×1個、B商品×2個が今年中に売れたとすると
在庫となったA商品1個の商品単価は
44元×1×17.15=754.6 となって四捨五入すると755円になりますが、
A商品の仕入れ時は2個で1509円だったのに
1個755円が商品単価とすると755×2=1510で
1円多くなってしまいます。
それでもA商品の単価は755円としても問題ないでしょうか?
それとも、合計1509円となるようにどちらかを1円引いた方が宜しいでしょうか?
②
また、輸入仕入れのため
「仕入原価」を求めるには
他に「仕入高」として計上している代行手数料/オプション/その他/国内送料/国際送料/関税/消費税・地方消費税/通関料の合計800円も
質問①の商品単価にプラスして計算しないといけないと思っているのですが、その計算は
今回4点の商品を仕入れたので各商品1点あたり
800÷4=200円をプラスして仕入単価とするで間違いないでしょうか?
(A商品の場合だと仕入原価は755+200=955円)
それとも商品代金以外の仕入高は各商品ごとに計算する必要がありますか?
その場合だと計算が複雑で、国際送料や関税・地方消費税・通関税などは計算方法がわかりません。
どのようにすれば宜しいでしょうか。
③
年内に同じ商品を再度仕入れた場合、
商品単価は「最終仕入原価法」で計算するとのことですが
仕入れ1回目のA商品単価が755円、
仕入れ2回目のA商品単価が800円 だったとすると、
両方のA商品単価も仕入れ個数もしっかりと把握していても最終仕入原価法を必ず用いて計算するべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
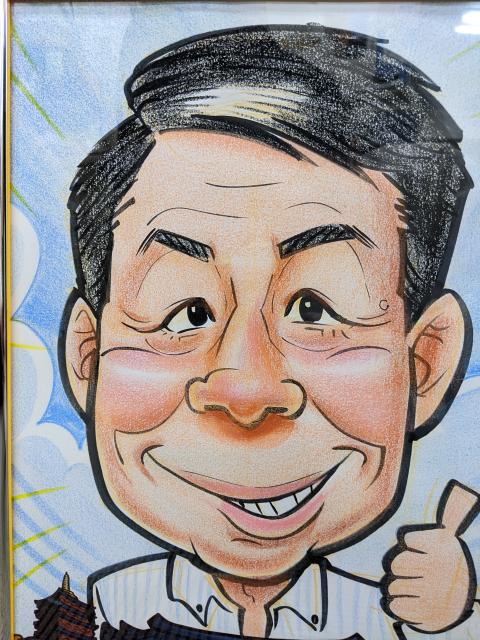
項目ごとにお答えします。
①
質問者が採用している棚卸資産の評価方法で計算した単価に在庫数量を乗じた金額を、円単位で切り捨てた金額になります。
たな卸品の評価方法には総平均法や移動平均法もあり、銭単位で計算しているところもありますのが、在庫として計上する際には現在の通貨単位が円ですので、円未満は切り捨てることになります。
原価計上された単価と異なることになります。
②
購入したたな卸資産ですので、取得価額に含めるのは販売のために要した費用になりますので、記載のうち消費税・地方消費税を除いた金額となります。
しかし、消費税の経理方法を税込み方式としている場合には、記載のすべてが含まれることになります。
また、不随費用の按分については項目ごとに合理的な按分方法を継続して使用することになります。
商品1点当たりの仕入れ単価が1円であったり10,000円であったりする場合もありますので、単純に1点当たりで按分することは合理的とは言えません。項目によっては、金額按分などの採用を考えてはいかがでしょうか。
エクセルにあらかじめ計算式を入れておけば、簡単に計算できると思います。
③
在庫の評価方法については、届け出をした方法又は届け出をしなかった場合は法定評価方法の最終仕入原価法を用いることなっています。
ご質問では届け出をしていなかったようですので、最終仕入原価法となります。
年内最後に仕入れたときの単価を用いることになりますので、800円だったら800円、700円だったら700円となります。
なお、評価方法の届け出期限は、新たに事業を開始した人は開業した年の確定申告書の提出期限までに、開業2年目以降に評価方法を変更しようとする場合には、変更しようとする年(「翌年」ではない)の確定申告書の提出期限までとなります。
ご回答いただきありがとうございます。
①
・質問の通り
A商品の仕入れ時は、2個で1509円でしたが
一個あたり44元×1×17.15=754.6 → 755円となり、
棚卸しの原価計算時は仕入れ時より単価が1円多くなってしまいますがそれでも問題はないということで宜しいでしょうか?
②
免税事業者のため消費税の経理方法を税込み方式とし、消費税・地方消費税及びその他購入付随費用も全て含めて計算するようにいたします。
(因みに仕入れ時は、代行手数料/オプション/その他/国内送料/国際送料/関税/通関料/消費税・地方消費税など全て「仕入高」として計上しております。)
・その棚卸時の仕入原価の計算ですが、
各商品、1点あたりの仕入れ単価にそこまでの差がない場合は均等に付随費用を按分しても問題ないでしょうか?
・また、今後各商品単価に差が出てきた場合は付随費用を均等に按分していると何か問題が生じますでしょうか?
・例えば、今年海外から下記の仕入れを行ったとします。
【1月】
A商品100円×10個=1000円 購入
B商品200円×10個=2000円 購入
代行手数料などの付随費用合計が500円
1月の合計仕入→1000+2000+500=3500円
【6月】
C商品300円×10個=3000円 購入
D商品400円×10個=4000円 購入
代行手数料などの付随費用合計が1000円
6月の合計仕入→3000+4000+1000=8000円
棚卸しの際に
A商品1個 B商品2個 C商品3個 D商品4個
の在庫が残っていた場合、
各商品単価×在庫数に加えて
1月に仕入れたA商品とB商品は
合計付随費用500円÷20個(1月の合計仕入数量)=25円、
6月に仕入れたC商品とD商品は
合計付随費用1000円÷20個(6月の合計仕入数量)=50円
を足して下記のように仕入れた日ごとに付随費用を按分して仕入原価を求めても大丈夫でしょうか?
A商品の合計在庫額 → (100×1)+(25×1)=125円
B商品の合計在庫額 → (200×2)+(25×2)=450円
C商品の合計在庫額 → (300×3)+(50×3)=1050円
D商品の合計在庫額 → (400×4)+(50×4)=1800円
重ねて質問失礼いたします。
宜しくお願いします。
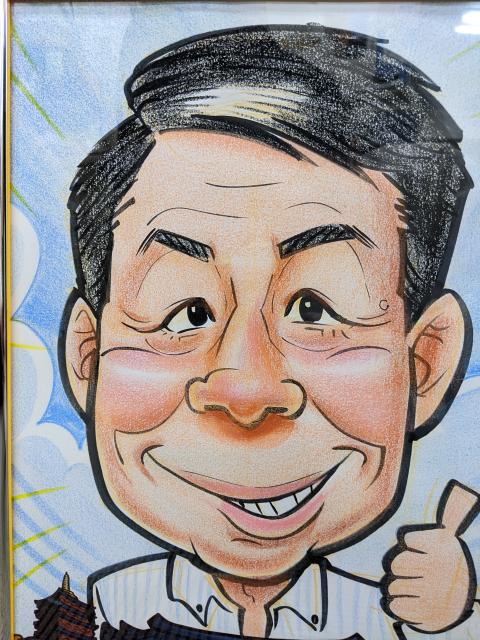
ご質問、ありがとうございます。
①
期末の棚卸高は、棚卸品の単価(通常は銭単位で計算しているところが多い)に在庫数量を乗じた金額を、円単位に切り捨てた額になります。
ご質問のケースでは期末在庫数量が1個ですので、754.6円→754円になります。
②
ご質問の付随費用の按分方法ですが、法令での規定はありませんので「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算」されていればよいと考えられます。
ご質問では、仕入れ個数を用いた按分方法になっていて、計算に誤りはありません。
他の方法として1個当たりの金額で按分した方法もあり、次のとおりです。
1個当たりの付随費用=付随費用/仕入金額合計×仕入単価
付随費用(1個当たり)
A商品 → ( 500/3,000)×100=16.66円
B商品 → ( 500/3,000)×200=33.33円
C商品 → (1,000/7,000)×300=42.85円
D商品 → (1,000/7,000)×400=57.14円
合計在庫金額
A商品 → (100円+16.66円)×1個= 116.66円 → 116円
B商品 → (200円+33.33円)×2個= 466.66円 → 466円
C商品 → (300円+42.85円)×3個=1,028.55円 → 1,028円
D商品 → (400円+57.14円)×4個=1,828.56円 → 1,828円
合計 3,438円
ご質問の商品ごととの金額対比ではプラスマイナスがありますが、ご質問の合計額は3、425円で合計金額の差は少額になりますので、このケースでは問題がないように思われます。
仕入品購入単価の最低値と最高値の幅が大きいのか小さいのかわかりませんが、価格幅が小さければ差は少なく、価格幅が大きければ差も大きくなります。
また、同時仕入れの時の単価が高い商品の方が、個数按分した場合には単価は小さくなります。
取扱品の価格構成にもよりますが、個人的には金額按分をお勧めします。
なるほど。よく理解できました。
非常にわかりやすくご説明ありがとうございます。
付随費用の按分は金額按分を採用することといたします。
度々質問して大変申し訳ないのですが追加で他に不明な点がございます。
④
・1/5にA商品100円を10個仕入れ、
手元に届いた際に1個不良品が見つかり
仕入れ先から100円の返金があったとします。
その不良品を自分で修理して
1個1000円で販売し1/10にその修理品が売れたとすると、
その際の勘定科目等の仕訳はどうなりますでしょうか?
修理費用が発生しなかった場合と、
発生した場合も教えていただけると幸いです。
・またこの修理品が今年中に売れず在庫となった場合、
この商品の仕入原価は
代行手数料などの付随費用は返金されていないため、
商品単価0円(商品代金は返金有)+1個あたりの付随費用
という計算になるのでしょうか?
付随費用の一部も(例えば代行手数料のみ)返金された場合も教えていただけると幸いです。
⑤
質問④とは逆に、返金もなく修理も不可能で自己破棄した場合は勘定科目等どのような仕訳になりますでしょうか?
⑥
1/5に、A商品100円を10個仕入れ、
そのうちの1個をプライベート用にした場合、
勘定科目は
事業主貸 ** / 自家消費 **
で間違いないでしょうか?
調べたところによりますと、金額は商品の仕入価格と販売価格70%のいずれか高い方にするようにと目にしたのですが、
販売価格に関しては日々価格変更を行なっているため毎回価額が異なります。
この場合はどうすれば宜しいでしょうか?
何度も本当に申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
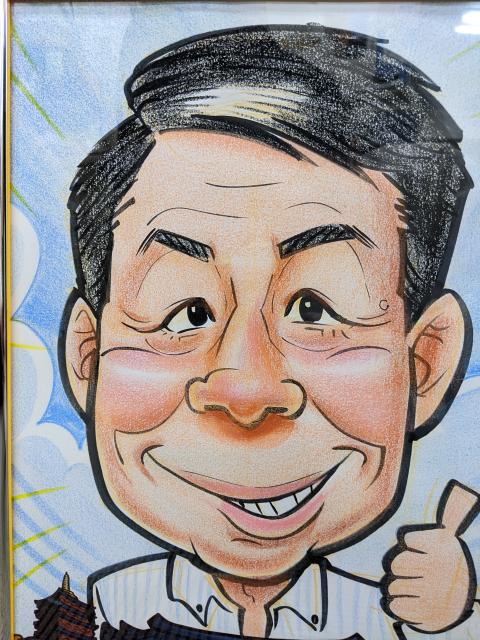
返品処理についてのご質問ですが、まず返品か又は値引きかにより異なります。
④
このケースでは「返金があったら」としていますので、返品になります。
返品であれば本来は輸入先へ送り返すことになります。
送り返すことをしないようですが、返金を受けていますので商品の所有権は輸入先にあります。輸入品の場合、送りかえす費用を考えて輸入先から商品を国内廃棄処分するよう求められる、又はこちらで自由に使用・処分してよいのかなどの両者間の取り決めがあると考えられます。
取引上の問題が出てくる可能性がありますので、仕訳の前に事実関係がどのようになっているのか不明ですので、回答は出来かねます。
⑤
上記④をお答えできない状況なので、この質問についても回答は出来かねます。
⑥
仕訳は、事業主への債権を増やし反対に費用を減らしていますので、ご質問のとおりで問題ないと考えます。
販売価格の評価額は、プライベート利用した日に販売したと考えますので、利用当日の価額を使用してください。
詳細なご質問になってきましたので、今後は専門家である税理士などに直接ご質問されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
説明が不足しており申し訳ございません。
④⑤ですが
実際は商品単価全額の返金を受けていないため、
正しくは「値引き」になります。
輸入先からは販売できるならしてくださいと言われております。
本投稿は、2021年11月06日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
























