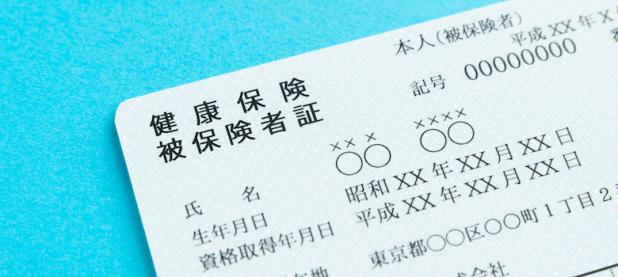建設仮勘定について
2年間ほど掛けて、建物付属設備のいくつかを更新することになりました。支払いはかなり大きな金額になるので、5~6回払いの予定です。
1社に全て発注し契約書を結び、表紙には工期は着工日〇年〇月、竣工〇年〇月と記載してあります。その間、一部完成したものは事業で使用しますが、契約書にある竣工日まで、建物の引き渡しは受けていないとの認識から、資産計上せず、支払ごとに建設仮勘定で処理しようかと考えております。(期をまたぐ)
その後、竣工後、建物仮勘定から、資産計上(引渡し後、資産計上と除却を同時に行う)、雑費、公害対策費などの費用に振り替えようと考えているのですが、このような処理で問題ないでしょうか?
税理士の回答

完成し、引渡を受けたものから、順次、資産計上し、減価償却費を計算した方が有利と思います。
固定資産の取得日は、引き渡し日の属する事業年度ですから、その事業年に建設仮勘定から該当する科目に振り替えられたら良いと考えます。
しかし、除却損は、除却した年度の、経費となります。

消費税上の論点も含みますので、顧問税理士の方に相談し、還付を受けるのか、受けるのであれば、課税事業者選択届を出すのか、何時の仕入れとして支障が無いのか等検討されても宜しいのかと存じます。
ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。あと、仕訳ですが、支払ごとに撤去費用も含めて建設仮勘定でよいのでしょうか?撤去費用は資産に含まれないので建設仮勘定ではなく前渡金になるかと考えたのですがこのような一括した処理で問題ないでしょうか?(複数工事なので支払ごとに撤去費用だけ分けるのは難しいため、業者から撤去完了報告を受けた後、建設仮勘定から除却損に振り替えする考え)
それと、除却ですが、業者が設備を取り外し、敷地内に廃材としておいておき、産廃業者が定期的に回収してくれる予定なのですが、解体された複数の廃材をまとめておいてある為、産廃会社が何の設備を回収したか把握できないため、〇〇設備廃棄との詳細な廃棄証明がとれません。その場合、鉄くず〇〇キロ回収との清算書をもらうだけでも廃棄証明になるのでしょうか?

・建設仮勘定で問題ないと思います。完成時に、一部、固定資産除却損への振替となります。
・清算書で廃棄証明になると思いますが、廃棄の設備と解体後の鉄くずの写真を残された方が、後日説明しやすいと思います。
ご回答ありがとうございました。初めての固定資産担当だったので大変勉強になりました

過去の類似の処理の確認し、処理の意図を確認した上で、現在の状況か、選択肢として何が取れるか。
法人にとって何が有利で、税務上のリスクは何で、どう軽減できるか。
ご自身で整理し、顧問税理士の方に事前に確認しておかれるとよろしいのかと存じます。
選択肢の検討は慎重にされても良いかもしれません。
ご回答ありがとうございます。過去の類似事例では、設備の新規更新では廃棄証明はとっておらず、新しい設備の引渡し時に固定資産の計上と古い設備の除却を同時に行い、撤去費用は新しい設備の資産に加算していました。
この処理では除却時期がずれるのと、撤去費用が除却損ではなく固定資産になってしまうので、会社にとって不利になるものと考えご相談した次第なのですが、不利にはなるものの税務上のリスクは少ないのでしょうか?

顧問税理士さんには確認されましたか。
されれば、ご質問者の方の責任は軽減されます。組織上。
踏まえて、設備の更新が契約上明らかで廃棄証明は取る必要が無かったのかもしれませんね。
今回も、同様に言えるのかどうか、といった検証をしたうえで、ご確認されてもよろしいのかと存じます。
タイミング、についても規模にもよりますし、部分的な取り換えにより、取り換えた部分が事業の用に供せるのであれば、その時点で計上、償却も出来るでしょう。
それが過去はどうであったか、今回はどうか、ご自身で検討した上で、確認をする。
撤去費用については、費用処理する方法がなぜ取れず、今回はどうなのか。
会社にとって不利な処理であれば、税務上は安全。
今回は、税務上のリスクとしては、どのようなものがあり、リスクを軽減するには何をすべきか、それはこれからのことなのでおおむね対応することができるでしょう。
その理解が正しいか、安全か、ご自身の責任を軽減するには、顧問税理士の方への確認が必要です。
ご回答ありがとうございます。整理検討して顧問税理士に確認したいと思います。

会社にとっての有利なもの、というのは税務調査等を受けない範囲での合理的な会計処理の選択、というものが前提。
100%完全な処理をされている会社は無いのですから。
その上で、法人税、消費税上の検討をし、かつ、相談者自身としても身の保全を図れる範囲の検討をされてもよろしいのかと存じます。
その際、顧問税理士に専門的な判断を聞いた、確認した、ということであればそれにまつわる税務上の論点を彼の責任の下に方針を決めることができます。
全てではありませんが、重要なもの、また、会社の全体の概況を把握している方の視点から、といった確認のされ方をすれば、然るべき対応をいただけるものですから。

費用に出来るものを資産計上していたら、会社不利で、もちろん税務上のリスクはありません。
今回の建物附属設備の更新について、新規資産の取得価額(付随費用も含め)、事業供用日、廃棄した資産の除却損については、後日の税務調査で間違いなく確認されると思います。
そのためにも、説明できる資料などの整理が必要と思います。費用か資産かグレーな部分は、顧問税理士にご確認ください。
本投稿は、2018年08月01日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。