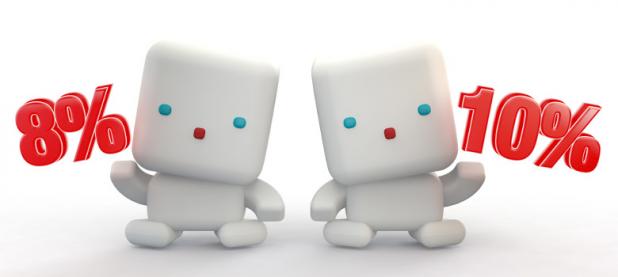公証人は消費税の納税義務者となることがあるかどうか。
公証人役場が簡易課税を適用した場合、簡易課税の事業区分において「第五種事業」に区分されます(国税庁ホームページ:質疑応答事例集、日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)より)。
しかし、消費税の非課税の規定に「公証人の手数料を対価とするもの」が列挙されています。
そもそも、公証人役場が消費税の納税義務者となることはあるのでしょうか?
税理士の回答
公証人法の手数料を対価とする役務の提供は、消費税法第六条、別表第一の五ハで非課税とされていますので、消費税の納税義務者となることはないと思います。
消費税は先ず、課税事業者かどうかを判定し、簡易課税は課税事業者の申告納税方法の選択肢のひとつに過ぎませんので、ご質問の考え方は順番が逆になっていると思います。
ご回答ありがとうございます。
公証人の手数料を対価とするものが非課税のため、公証人役場が課税事業者になることはないのであれば、簡易課税を選択適用することもありませんよね?
なのになぜ、簡易課税の事業区分に「公証人役場:第五種事業」と記載があるのでしょうか??
簡易課税を適用する機会がないのであれば、事業区分に記載する必要性がないように思うのですが。
日本標準産業分類で「722公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所」と一つの分類コードで記載されており、単に日本標準産業分類の記載を引用しているためだと思われます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月21日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。