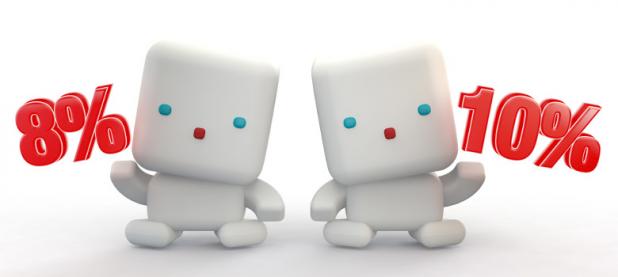コンクリート圧送の簡易課税 事業区分について
コンクリートの打設作業をコンクリートポンプ車を利用して行う仕事をしております。
最近、税務調査が入りまして、税務署の方から事業区分は第3種ではなく、第4種になる可能性がある。と言われました。
作業の際に必要な、セメント、砂を自社で仕入れており、お客様には有償で請求しております。
税務署の方曰く、
その仕入れは売り上げの一部ですよね?
全てのお客様にセメント代は請求してないですよね?
ですので、多分第4種になると思います。
と言われました。
こちらが、では、第4種になると言う理由を法的に説明できますか?と問いただしたところ、
うーん…それは事務所に帰ってちゃんと調べてきます。と言われました。
税務署の方はちゃんとした根拠もないのに税金を取る為なら何でもするんだな、と感じました。
こちらとしては、売り上げの一部であろうが第3種に引っかかる項目がある時点で第3種ではないのか?
お客様に配る料金表にも必ずセメント代として記載しており、ポンプ業界ではセメント代の有償はおかしくない事なのになぜ?
と思っております。
国税庁のHPや、他のHPでも色々調べましたが、そもそもユーザーにわかりにくく、にごわしたおおむねなどの言葉で記載してある、国税庁にも問題かと思います。
お互い腑に落ちない気持ちで消費税率10%上がるのは納得がいかないので、お手数なのですが、専門の方々にご指導頂けたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します!
税理士の回答
税務署で35年法人税調査をしてまいりました経験から回答させていただきます。争点整理してみますと、税務署は、すべてのお客にセメント代を請求していないですよね?と質問していることから現場において、セメント・砂を現物支給している業者がいて、その分請求していないのではないか(単なる手間賃仕事でないか)では4種事業となると思っていませんか?当社は自前でセメント・砂を仕入れコンクリートミキサー車でセメントを製造している業者ですよね。常識としてコンクリート屋に材料を現物支給する建設業者は聞いたことないですよね。署の担当者に業種・業態の理解をしてもらい、当案件は製造に該当する第3種事業で正しいことをしっかり主張し、納得してもらって下さい。
ご丁寧なご返答ありがとうございました。
記載に語弊があったので、お詫びと訂正をいたします。
当方、コンクリート圧送業と申しまして、型枠にコンクリートポンプ車を使用し、流し込む作業をしております。その際に、コンクリートミキサー車とコンクリートポンプ車をドッキングさせ、生コンはポンプ車の後ろのホッパーの中にミキサー車が入れていきます。要は、ミキサー車と左官屋さんの間の役割の業種になります。
あと、セメントと砂ですが、ポンプ車にミキサー車の生コンを通す際、先行材として、ポンプ車に1袋づつホッパーに入れ、練って通してから、ミキサー車内のセメントを入れます。多い時には2体~3体づつ使う現場もあります。その使用理由の一つはミキサー車内のセメントが詰まらないようにスムーズに送る為です。
他にも、数は多くないのですが、まれに当方が基礎の全てを任される事があります。そうなった場合は、左官屋さんの手配、生コンの手配、土間屋さんの手配等々全て自社が元請として行うこともあります。そういった場合にはもちろん生コン屋さんの支払いは当社になります。
何度もお手数なのですが、上記を踏まえますと第何種が妥当でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
お忙しい中、詳細な業種・業態のご説明いただき有難うございました。
ほぼ私の思っていた通りの説明でした。第3種なのか、第4種なのかの判断基準ですが、第3種の場合、例えばサッシとガラスの隙間又はサッシと建物の隙間にコーキング剤を使用して埋め込む仕事が該当します。第4種ではガス管工事業者がガス管の無料支給を受けて行うガス管の埋設工事、麦の支給を受けて行う製粉、果物等の支給を受けて行う缶詰加工、食料品加工業者が貝、えびの支給を受けて行うむき身の製造等が該当しますが、ご覧のように第4種は材料支給を受けた手間賃の要素が強い仕事となっています。これを踏まえて貴社の業態を見るとコンクリート、砂は自社で仕入れをしていて他社から無償支給・有償支給されてはいないことから、性質及び形状を変更する製造業第3種に該当すると思われます。いずれにしても当社の業態を調査担当者に冷静に説明し納得してもらってください。だめなら税務署の上司(統括官)へ説明したらわかってくれると思いますよ。諦めずに頑張って下さい。
お忙しい中、再度ご返答頂きありがとうございました!!
ご返答を参考にさせて頂き、諦めず説明したいと思います!
貴重なお時間を割いて頂き、本当にありがとうございました!
本投稿は、2018年10月16日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。