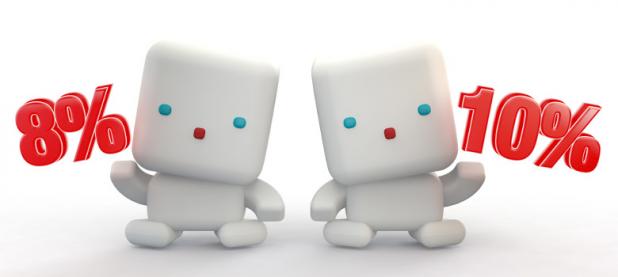輸入消費税の還付について
昨年から輸入業を始めました。最初の消費税の申告なので税務署に相談に行ったら、資本金が1千万未満なので納税義務はなく申告は不要(できない)と言われました。
スタートアップで売上が少なく輸入商品の在庫が結構あるので消費税の還付を見込んでいました。
そこで質問なのですが、
①税務署のいうとおり、納税義務はなく申告はできないのでしょうか?
②輸入の際に消費税を支払っていますが、納税義務がないとしたらこの消費税はどのように還付されるのでしょうか?税務署の言っていることが矛盾しているように思えます。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答
昨年に事業を始めた個人事業者の前提で回答します。
そもそも、輸入消費税は還付されるものではなく消費税の納税額の計算で受け取った消費税から差し引く(仕入税額控除といいます)ものですから、認識が間違えています。
①基準期間等の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者の場合、課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならない限り課税事業者になれません。
貴方が昨年末までにこの手続きをしていないのであれば、税務署の言っていることは正しいです。
②免税事業者が消費税の還付を受ける方法はありません。
免税事業者は消費税の申告納税義務がない一方で還付を受けることも出来ません。つまり納税の義務がない反面、還付を受ける権利もないということなので何ら矛盾しません。
支払った消費税は仕入などの経費になります。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。税務署からも同様の説明を受けました。輸入消費税は仕入税額控除されるものという点の説明も同様に受け、制度の仕組みは理解しました。
しかし、その点に矛盾があると思います。消費税の申告納税義務がないという説明なのに、輸入に係る消費税の申告納税義務はあるという点です。
同じ消費税として同じ国(納税先が税関か税務署の違いはありますが)に納税するにもかかわらず、なぜ納税義務に差が発生するのかが理解できません。
消費税というのは日本国内で消費されるものに対して課せられるものなので、輸入品は日本国内で消費されるため輸入時に消費税を納めることになります。
貴方が日本国内のお店で普通に買い物をしても消費税を払いますよね。
国内のお店で買い物をする時に消費税が付加されるのが、輸入品は税関で消費税が付加されるということです。
貴方の理屈でいうと、普段の買い物で消費税を支払っているのも理解出来ないということになります。
また、消費税は事業者が納税しますが、最終的に負担しているのは上記の通り消費者です。
貴方が輸入したものは日本国内で販売するのでしょうから、その時に消費税を付加して販売するはずです。
課税事業者であれば、販売時に受け取った消費税から輸入時に支払った消費税を差し引いて納税しますから、何もおかしなことはありません。
輸入時に支払う消費税だけを捉えて考えるから、理解できないのだと思います。
普段の買い物で払っている消費税と輸入消費税は全く別物だと認識しております。普段の買い物は事業者を通じて間接的に国に払っている・対応する売上がない、輸入消費税は国(税関)に直接払っている・対応する売上があるという点が違うからです。
前者ではその事業者が消費税申告をして初めて国に消費税が納付されます。後者では私が輸入申告時に国(税関)に消費税を既に納付した後に国(税務署)で消費税申告をして精算を受けます。
輸入時に支払う消費税だけを捉えて考えているとのご指摘はそのとおりです。しかし、輸入消費税は既に国(税関)に直接納付しているのだから精算を受ける権利があるように思えます。
同じ国で同じ税なのに税務署では免税事業者、税関では課税事業者というロジックが理解できません。法律に書かれているのでしょうか?
税務署での精算がご説明のとおりできないとすれば税関での精算(免税事業者扱い)ができる可能性はありますか?
法律は調べてみました。消費税法9条1項の納税義務の免除の特例の範囲が同法5条1項に限定され、同条2項による輸入消費税の納税義務だけ残るため還付不可、という理解になりますか?
輸入時に支払う消費税だけを捉えて考えているとのご指摘はそのとおりです。しかし、輸入消費税は既に国(税関)に直接納付しているのだから精算を受ける権利があるように思えます。
→極端な話、貴方が輸入したものを0円で販売すれば、課税売上に係る消費税0円-輸入時に支払った消費税〇〇円=還付〇〇円です。
但し、繰り返しますが還付を受けることができるのは課税事業者だけです。税関での還付もできません。
お店は販売商品の仕入時に仕入先に消費税を支払いますが、このときの消費税の納税義務者は仕入先で、仕入先が消費税を納める先は国です。販売商品の輸入=販売商品の仕入なのですから、輸入者は上記の仕入先と同じ立ち位置です。
消費税法9条1項の納税義務の免除の特例の範囲が同法5条1項に限定され、同条2項による輸入消費税の納税義務だけ残るため還付不可、という理解になりますか?
→概ねそのような理解でよろしいかと思います。
還付の権利は納税の義務を履行して初めて得られます。
仮に、免税事業者が輸入消費税の還付だけを主張して、その輸入したものを販売した消費税は納税せずに収入とする方が矛盾していると思います。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、輸入消費税の還付だけを主張するのはおかしいですね。
ご丁寧なご対応どうもありがとうございました。制度全体の理解が深まりました。
例えが悪かったので訂正します。
販売商品の輸入=販売商品の仕入ですが、仕入先は販売先から受け取った消費税を国に納めます。
国内で多段階に仕入が発生することで消費税が累積していくことになりますが、累積したままだと最終的に消費税を負担する消費者が支払う消費税は10%ではすみません。これを排除する仕組みが課税事業者の仕入税額控除です。
輸入の場合は、消費税法が適用されない海外の輸出者に消費税の支払を求めることができないため、国内で初めて商品を受け取った輸入者に消費税の納税を求めているに過ぎませんが、上記の仕入税額控除の仕組みで税関に支払った消費税を控除できることになります。
但し、課税事業者であることが前提です。
理解しやすいご説明どうもありがとうございました。
一律に基準期間により納税義務を判定するところに立法上の問題があるように思いました。多段階課税であればすべての事業者が納税義務を負担しなければ公平な課税にならないからです。
とはいえ、今回の件は制度として課税事業者選択届出書があることを私が知らなかっただけですね。
全体像が理解できました。本当にありがとうございました。
仰る通り、全ての事業者が消費税の課税事業者にならなければ根本的な解決にはなりませんが、実質的に免税事業者の消費税の益税化を排除することになるのが令和5年10月1日施行のインボイス制度です。
本投稿は、2022年06月18日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。