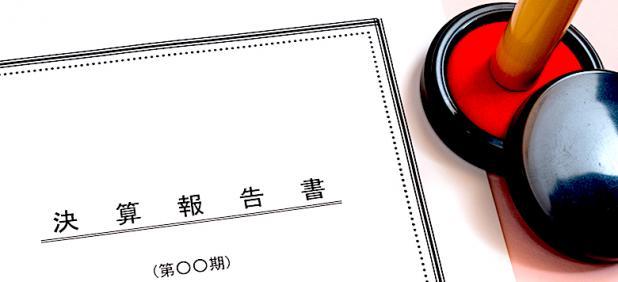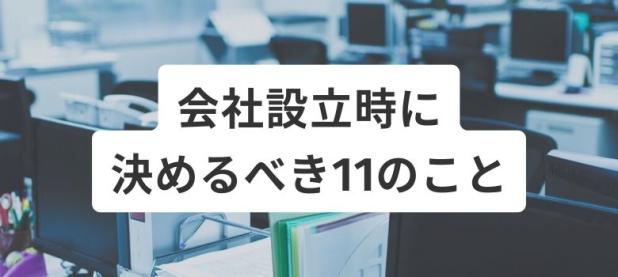海外FXでの合同会社設立について
関連ワードでヒットしたものに目を通しましたが、同じ質問がなかったのでこの場を借りて質問させていただきます。
表題の件で2点質問があります。
私は会社員でFXを去年から始めました。
①後々、安定して利益が出た際は合同会社を設立したいと思っていましたが、
今年はマイナス着地しそうなので、来年以降の利益と損益通算させる為に合同会社を設立するのもありかと考えています。
設立前の損益や経費であっても過去三年前?までの分は設立後の確定申告で申告できると、どこかで見たのですがこのあたりの正しい情報をご教示いただきたいです。
②FXでの会社設立は難しいことを理解しているので
いくつか事業として記載出来るものを考えていますが、
FXとは全く関係ないことは同じ会社の事業として書けるものでしょうか?
私は保護猫のボランティアをしており、FXの利益をこれらに係る費用に充てたいのですが
保護猫譲渡で利益は得ないので通常はNPOになるところを
同じ会社にすることでFXの利益とボランティアの経費を相殺できないかと考えています。
これは実際可能でしょうか?
調べた限り必要な免許はなく、扱う頭数上、自治体への申告も不要なようです。
イレギュラーのためネットで調べても回答が得られませんでした。
以上2点について、複数の方からご意見いただけると助かります。
税理士の回答
➀個人の損失を設立する法人に付け替えるということですか?そうであれば自身の経営する法人でも法人と役員個人は人格も財布も適用される税制も全くの別人なので出来ません。
また、設立後も法人の所得と個人の所得の損益通算は一切出来ません。
➁会社は定款に記載された目的以外の事業は出来ません。より具体的なことは会社法に詳しい弁護士か司法書士にご相談ください。
そもそも、NPO法人とは非営利活動法人です。投機性の高いFXをNPO法人で出来るとは思えませんが、こちらも特定非営利活動促進法等に詳しい弁護士にご相談ください。
ご回答有難うございます。
少し伝わり切っていないように思ったので補足します。
①前提として、法人税基本通達2-6-2に「設立中の法人について生じた損益は、当該法人の、その設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができる」とあるので伺った次第です。
確かに”個人の損失を設立する法人に付け替える”と言われると出来なさそうとは自分でも思いますが、”最初の事業年度に生じた損益としてならどうか?”という質問です。
②「FXとは全く関係ない事業も同じ定款に記載できますか?」という質問です。
通常はNPOになると言っただけで私もNPO法人にするとは言っていません。
NPO法人でFXをするとも言っていません。
お手数おかけしますがご確認宜しくお願い致します。
➀会社法上の設立中とは会社設立の発起から登記完了による成立までのことですから、当初のご質問に記載されているような設立発起以前の行為は発起人の行為ではありませんから、会社の所得にはなりません。貴方のいう最初の事業年度というのが何を想定されているかわかりませんか、すくなくとも設立発起をして発起人としての行為でなければ、成立後の会社の行為にはなりません。
法人税法は上記の会社法の規定に則ったものと解されますが、会社法については弁護士か司法書士にご相談ください。
➁会社は定款に記載された目的以外の事業はできませんから、営利法人であれば行おうとする複数の事業を定款の目的に記載すれば済む話です。現に複数の事業を行う法人は山ほどあります。
設立前の損益や経費であっても過去三年前?までの分は設立後の確定申告で申告できると、どこかで見たのですが
→常識的に考えて会社設立発起から登記による会社成立に3年掛けるのはあり得ませんし、聞いたこともありません。
ご回答有難うございます。
①もはや補足のために調べたおかげでわかったようなものですが、設立中の損益だったらできるということですよね
どれぐらい前の期間なのか?という質問だったので「発起から登記完了による成立まで」ということがわかったのでOKです。
”当初のご質問に記載されているような設立発起以前”とあったのでいつのことか指定したかな?と思いましたが「今年はマイナス着地しそう」と述べてるように年内のまだ先のことを考えて伺った次第です。
”3年”は何で見たか未だ見つけられずにいますが、経費の場合は遡っていつまでと決まっていない、とあったので理解しました。
②「いくつか事業として記載出来るものを考えています」と述べたように、複数の事業を定款に記載できることはわかっている上で「FXとは全く関係ない非営利の事業も書けますか?」という質問でしたが、より詳細なことは弁護士か司法書士に確認いたします。
有難うございました。
本投稿は、2023年08月10日 04時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。