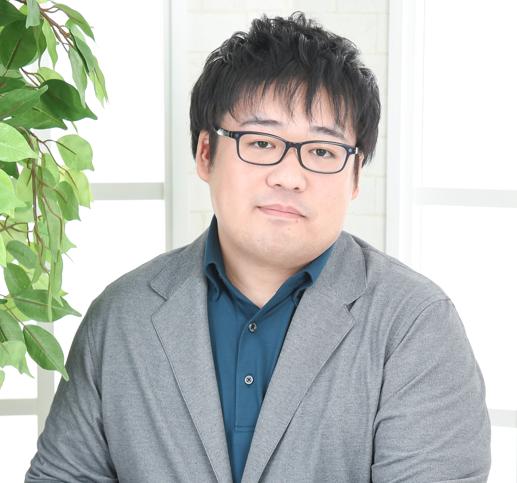夫の収入を妻名義の口座で住宅の貯蓄していました。
贈与税についての質問です。
結婚、18年の夫婦です。この度6000万の新築戸建を購入する事になりました。結婚してから、私は(妻)15年専業主婦でした。夫のお給料から生活費を残して、ボーナスもほぼ全額、私の口座で貯蓄してきました。専業主婦だった為、夫もお金の事は私に全てまかしていました。今回自己資金で3300万いれて、残りは主人名義でローンをくみます。住宅の決済日が近いのですが、妻の口座から主人の口座へ全額移動する予定でいましたが、贈与税がかかるとは、お恥ずかしながら知りませんでした。18年コツコツと貯めてきたので、どうしたものかと動揺しております。こちらで似たような質問を読ませていただいて、お互い贈与の意思はなく、一つの口座にまとめた方が管理しやすいだろう、と考えていました。この場合は名義人口座?で課税対象外となるのでしょうか?贈与税はかかってしまうのでしょうか?もしそうなってしまったら無知のあまり主人に申し訳なく思います。
とても不安です。宜しくお願い致します。
税理士の回答
その資金移動に贈与税はかからないものと考えます。
伺ったご状況から、自己資金3,300万円は旦那様の収入から貯蓄されたものとお見受けします。
この場合、ご認識の通り、名義預金(本来旦那様の預金だが、貴女様名義の預金になっている預金)と考えられます。
そのため、元々旦那様の預金で、旦那様の預金を移動するだけになりますので、贈与税の課税は生じないことになります。
なお、1点ご注意された方が良いことがあります。
購入される不動産の名義人は旦那様の単独名義にされた方が良いです。
ここで、不動産を共有名義にすると、旦那様から貴方様へ不動産の共有持分相当の贈与があったものと考えられます。
回答は以上です。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
森先生早速のお返事ありがとうございます。とても不安だったので安心しました。これからはよく調べてから物事をすすめていくようにします。
追加の質問で申し訳ありません。注意点をいただいた件で、私の(妻)父から、今回の物件を購入するにあたり、1500万の住宅贈与をうける事になりました。エコ住宅の為1000万は非課税、残りの500万は納税いたします。この場合の名義の持分は、全購入額の1500万を妻の持分、残りを夫の持分で計算すればよろしいでしょうか?
それから、父からの贈与の振込先は、
①夫の給料を妻名義で貯蓄していた口座へ②妻個人の口座へ
③決済とこれからのローンで使用する夫個人の口座へ(どちらにしても最後に全てのお金をこちらに移動します。)
3つのうち、どちらを振込先にしたらよろしいのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
ご認識の通りです。
持分はそれぞれがお金を出した割合に応じて計算されると問題ありません。
③を振込先にされて問題ないと考えます。
住宅資金贈与を受ける際に贈与契約書を作成されると思います。
贈与契約書の中で振込先指定口座として③の口座を記載されることで違和感がない振込にできます。
また、贈与税申告書にも財産の所在を記載する欄がありますので、契約書と同様に③の口座をご記載ください。
さらに念入りに記録を残すとしたら、通帳に「お父様から貴女様への住宅資金贈与」など贈与の詳細をメモされておくと安心かと存じます。
その他ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
先生、大変わかりやすくありがとうございます。続けて質問させてください。
贈与契約書は個人でパソコン等で作成してもいいのですか?それとも国税庁で決まった書類があるのでしょうか?
この契約書がないと、贈与する妻の父から直接、妻の配偶者の口座に振込まれる為、課税対象になってしまうのでしょうか?
心配なことばかりで何度も質問してしまって申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
パソコン作成で問題ありません。
また、決まった書式はありませんので、インターネットで契約書のひな形を探してご利用されるとよろしいかと存じます。
なお、契約書は自署押印をおすすめします。
贈与契約書によりあげる人、もらう人を明確にすることができます。
この契約書がないと、お父様から旦那様への贈与に見えてしまう可能性があります。
そうなると住宅資金の非課税が適用できない贈与に見える恐れがあるため、贈与契約書は贈与の証拠を残す意味でも重要な書類となります。
ご心配が解消されましたら何よりです。
わかりました。ありがとうございます。
パソコンで契約書は作成しましたが、この契約書があれば(ひな形参考で作成)主人への贈与ではないことが明確ですが、より明確にするには、私の個人口座に振込み、そこから、主人の口座に振込んだ方がよいのでしょうか?
本当に何度も申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
より明確にやり取りをされるなら、ご認識の通り、貴女様名義の口座に振り込まれた方がよいかと存じます。
その後、貴女様から旦那様口座へ振込みされる際には通帳へ経緯のメモを残されることをおすすめします。
上記よりさらに明確にするならば、旦那様口座へ振込みをせずにそれぞれの口座から取引先に支払う方法が最も明確かと思います。
わかりました。森先生、早急なお返事いただきましてありがとうございました、大変感謝しております。
お悩みが解消されて何よりです。
今後ともよろしくお願いいたします。
補足します。
登記名義については、建物に奥様の持分が必要です。
また、500万円について、相続時精算課税の適用を検討されることをお勧めします。
なお、来年の3月15日までに取得することが原則です。
森先生、振込先は③にして、住宅贈与契約書をしっかり作成し、税務署に申請時に必要書類と一緒に契約書のコピーを持参することにしました。
本当にありがとうございました。
鎌田先生ありがとうございます。はい、物件の名義は全体金額の、妻が贈与をうけた1500万分を持分といたします。
相続時精算課税について質問させてください。私の父が高齢の為、来年から暦年贈与(110万までの非課税贈与ですか?)をしたいと、話をいただいています。この場合は相続時精算課税は申請しない方がいいのでしょうか?いろいろと規定があって理解が難しいです。
どうぞ宜しくお願い致します
土地の名義に制限はありませんが、建物に持分が必要です。
相続時精算課税の条件は、お父様60歳以上、受贈者18歳以上で申告期限内の申告。
暦年課税だと贈与税がかかります。
失礼な話ですが、お父様が万が一の際には相続税という税金があります。
相続税には基礎控除という課税最低限があり、控除内なら相続税がかかりません。
その場合は、相続時精算課税を選択して贈与が2,500万円まで非課税。
相続税も非課税なのでお得です。
(計算式)3,000万円+600万円×法定相続人の人数
基礎控除を超える相続財産がある場合には相続税で精算で相続税がかかります。
なお、暦年課税(110万控除)でも、死亡から3年遡る贈与は相続財産に加算することとなりますので、節税にならない可能性があります。
お返事ありがとうございました。
相続精算課税を申請すると、来年から非課税の110万以内の贈与はうけれなくなりすか?
令和6年から暦年課税を選択できなくなります。
なお、令和6年以降の相続時精算課税には、別途110万円の基礎控除が新設されました。
森先生、鎌田先生
ありがとうございました。
何度もすみません。質問させてください。
来年、贈与の申請に税務署に行きますが、
もし、その後、税務署からお尋ねの通知がきた場合、書類の記入欄に、自己資金の銀行口座と名義人を書く箇所があるかと思うのですが、全ての自己資金を夫の口座に移動するので、夫の銀行口座を記入すれば問題ありませんか?
宜しくお願いします。
本投稿は、2023年08月27日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。