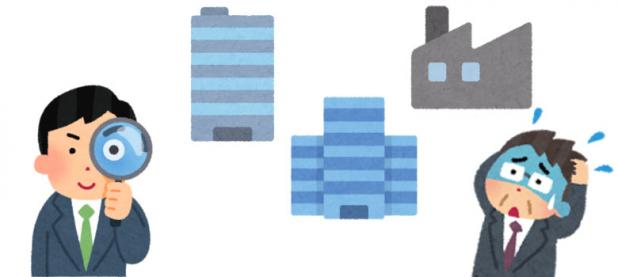仕掛品価額の算定
仕掛品の金額の算定に関して、お伺い致します。
今期、当社に税務調査が入り、仕掛品に対して疑義が生じました。当社はソフトウエアの開発と販売を行っている会社です。ベースになるソフトウエアを基に、顧客の要件に応じてカスタマイズを行い、製品にして納入しております。ソフトウエアの開発は100%内製で行っております。大型の案件の場合 1年を超える開発期間となり、今回は顧客と当社との間で調整がうまくいかず大幅な納期遅れと仕様変更・改修が発生して、大幅な仕掛品が積み上がって来ております。一方顧客への販売価額は約定されており、現状で行きますと大幅なマイナスが生じる可能性があります。
しかしながら、この仕掛品の価額はこの案件に関わる従業員の実労働時間にこの部隊の年間の経費で割り返した時間単価で算出したもので、外部からの仕入れコストはなく、当該部隊の給与(経費)として処理されており、実損は生じておりません。
そこで、今回の税務署の指摘は
①仕掛品は当該案件に関わる全ての労働時間x時間単価で計上し、実際に販売 売上計上時点で損失を計上する。
②その時点で損失計上したくないなら、期末時点で引当金等を計上しておく。
となっております。
当社としては、実損がない状態で、実態に即した損益に対応するために、仕掛品価額を実態ベースに調整した上で計上する。其の為の、内容の詳細・説明等のペーパーワーク
の準備をしておくことで説明義務・責任を当局に実証できるのではないか?
②の如く対応するのは、法人税を余分に発生させ支払う形となり、納得しがたいところです。
そこで質問ですが、上記のような状態に於いて、仕掛品の価額を実態に合わせた形で計上することは問題なのか? もしそうなら他にどのような対応策があるのかご教授ください。
以上
税理士の回答
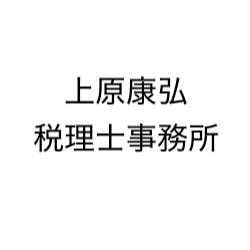
上原康弘
➀実損がないという意味がよくわからないのですが、、
一般にソフトウェアの開発に従事した人の人件費は製造原価に含め販売時に売上原価としてソフトウェアの販売により獲得した収益と対応させて費用化するものです。損益計算書の大まかな作りは下記のようになります。
➀売上高××
➁売上原価××←ソフトウエアの開発に従事した人のコストはここに集計
➂販売費一般管理費××←総務等の給与はここに集計
営業利益(➀-➁-➂)
売上原価に計上されるまでのプロセスは下記になります。
➃給与××/現預金××
➄仕掛品××/給与××
(開発に直接関与した人の給与は開発が完了するまで仕掛品に集計します)
➅製品××/仕掛品×× ←完成時
➆売上原価××/製品×× ←販売時に給与を費用化
ソフトウェアの開発に従事した人の人件費はソフトウェアを販売することにより得る売上に貢献するものである為両者を同じ期間に認識することにより企業の業績を適切に表せると思います、
➁は受注損失引当金のことを指していると思います。
受注損失引当金とは販売によって損失が生じることが明らかになった段階で将来生じるであろう損失を見積計上することです
上記の➄或いは➅の段階で今後の工数等を考えて売価を超える原価が発生することが確実な場合は下記のように引当金を計上します。
受注損失引当金繰入額××/受注損失引当金××
但し引当金は税務上費用として認められない可能性が高いので会計上費用処理した場合も税務上調整(加算)をして申告する必要があると思います。
以上から➀に関しては税務署に反論はできないように思います(全ての情報を把握していないので断言はできませんが・・)
➁に関しては会計上の話しで税務上は販売した時点で対応するコストは費用化するものと思います。
※一般に会計基準は費用を早めに計上することを要求しますが、税法は会計基準に比べて遅めに計上することを要求しています。
詳細なご説明有難うございました。色々各所調査しましたが、最終的には引当金にて対応するしか無いという意見が趨勢を占めております。税務報告に於いて、当期加算、翌期減算で行って来いの認識とは思いますが、事前に見積れる損失については、証憑を明確にし適正な仕掛品価額にて計上すれば、問題ないという見解もありましたが、会計基準からすれば、貴兄のご指摘通りの処理が正解と言う認識になりました。有難うございます。
本投稿は、2019年04月15日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。