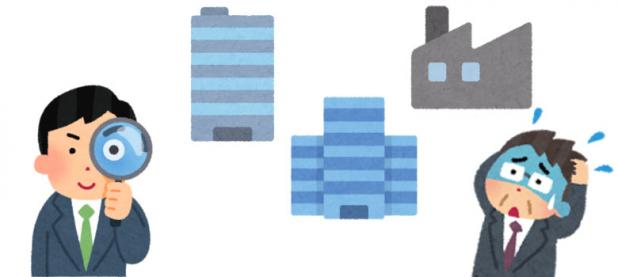国政徴収法39条について
国税徴収法39条について質問です。
この条文について素人でもわかるように説明していただけませんでしょうか?
特に責任の限度についての解釈がよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田中聡一
こちらの条文でよろしいですか?
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第39条 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第58条第1項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第142条第2項第2号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

田中聡一
この条文をまとめると、こんな感じになるかと思います。大分端折りますね。(条文の解説ですので、分かりづらくて申し訳ありません。)
1.滞納者が財産を無償又は著しく低額で譲渡し又は債務の免除その他第三者に利益を与える処分をしたこと
2.滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること。
3.上記の処分により権利を取得し、又は義務を免れた者に対し、その滞納国税の第二次納税義務を負わせる。
つまり第二次納税義務者は、例えば何かの所有権を取得した人や債務の免除を受けた人となります。
そしてその範囲ですが、
① 無償譲渡等の処分の時に滞納者の親族や特殊関係者である場合は、受けた利益の限度。
② 赤の他人の場合は、現存利益となります。
つまり無償譲渡等の処分の時に時価5000万円の土地が現在、4000万円だとしたならば、①は5000万円限度、②は4000万円が限度であるということです。
大変解りやすい説明感謝致します。
税務調査にて売上除外→役員賞与として600万円程指摘されました。
当然、個人に掛かる税金は支払います。
しかし、法人は他にも勘定科目の認識の違いで法人税、消費税、社会保険料等々ものすごい金額の追徴課税を課せられそうです。
法人は破産させるしかないと思っています。
しかし二次納税義務という言葉を知り、どこまでが私の責任の範囲なのかわからず毎日生きた心地がしませんでした。
私の解釈ですが、役員賞与として600万円を受け取ったわけですので600万円を限度として二次納税義務が発生するという認識でよろしいのでしょうか?

田中聡一
文面から判断するに、本件は国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)で想定されている取引ではないと思います。
インターネットの無料相談で一気に解決できるような内容ではございませんので、顧問税理士の先生がいないのならば、最寄りの先生にご相談されたほうが宜しいと思います。
それと、税務調査が一通り終わりましたら、いきなり法人の解散・清算を検討するのではなく、所轄税務署にて納税相談もされたほうが良いと思います。
換価の猶予等、色々と具体的な相談に乗ってくれると思います。
それと今後は納税意識を持って、ビジネスを頑張ってください。
本投稿は、2019年12月08日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。