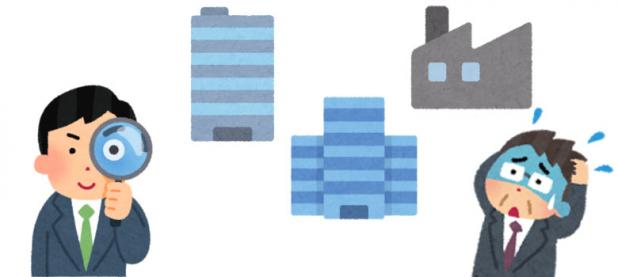職場の住宅補助についての質問です
はじめまして、地方の医師です。雇われ院長の転職話がきていて、特段福利厚生が無いので住宅補助をお願いしたいと考え交渉中です。賃貸料の50%まで補助という提示を受けました。
院長は医療法人の理事に就任するので立場は役員ですね。タックスアンサーNo.2600には「小規模な住宅である場合、賃貸相当額を受け取っていれば給与として課税されない」とあります。この賃貸料相当額というのがかなり低く(賃貸料の1割程度?)、法律上だけで言えば9割補助くらいまでは可能と考えます。
補助額アップ可能か向こうの顧問税理士に訊くと、50%以上はグレーゾーンになり、税務調査で目をつけられるので困難と言ってきました。
その事について国税局電話相談センターの何ヶ所かに問い合わせてみましたが、どこも「書いてある以上の縛りは無い」「豪華住宅と混同してるのでは」という回答でした。
その旨を顧問税理士に伝え、グレーゾーンの根拠が解らないと言うと、上手く説明できずに逆ギレし、自分で税理士探せば!と言ってきた次第です。
税理士さんがみんなこんな人ばかりでないでしょうし、税理士側の立場の率直な意見をお聞きしたく、このサイトにたどり着きました。アドバイス頂けますと幸いです。
税理士の回答
ご質問者様が契約して賃料を支払い医療法人から家賃補助を受け取るのか、医療法人が契約してご質問者様が社宅として借り受けるのかご記載の文面では判別できませんが、前者であれば、役員社宅ではなく家賃補助が5割であろうが9割であろうがご質問者様の給与として課税されるだけであり、後者であれば、ご覧になられたタックスアンサーNO.2600に記載された計算方法で賃料相当額を計算する必要があるということです。
医療法人に賃貸を契約してもらって、社宅として借り受ける事を想定しています。
賃貸相当額の計算は面倒だとは思いますが、かなり金額が低いと聞いておりますので、50%を超えたらグレーゾーンだというのはギャップがありますし、その根拠が解らないのです。補足頂けましたら幸いです。
ご覧になられたタックスアンサーNo.2600の2で賃料相当額を計算するためには、固定資産税課税標準額や建物の総床面積がわからなければできません。
固定資産税課税標準額は、所有者(家主)に教えて貰うか、実際に賃借人になって市区町村役場に閲覧請求しなければわかりません。
建物の総床面積は法務局で建物図面や各階平面図でわかるかもしれませんが、税理士の専門外ですので確定的な回答はできません。
上記のように、少なくとも賃貸物件の固定資産税課税標準額を取得することが困難なため、2に記載された賃料相当額の計算ができず、タックスアンサーNo.2600の2(2)の50%以上としていることが多いことから、グレーゾーンと言っているのでしょう。
早速のご返信ありがとうございます。
賃貸相当額がかなり低いというのは国税局の相談側から教えて頂いたことであり、検索すると賃料の平均1割弱の金額くらいとのことでした。
自分は1/4自己負担で3/4を法人負担してもらった経験はあります。
賃貸相当額は借りる家が決まらないと正確な計算はできませんがギリギリでなくとも、自己負担額が賃料の1/4(25%)で、3/4(75%)を法人が経費で落とした場合、法人が税務調査で突かれるということはあるのでしょうか?(他にやましい事があれば話は別ですが、純粋にその事だけで…。)
ご覧になられたアックスアンサーでも、計算方法等の規定が明記されていますので、調査があれば否認されるでしょう。
特に法人と役員間の取引は厳しく見られますので。
要するに明確な計算根拠が必要であって、概算計算は認めていないということです。
ご回答を読み返すと、賃貸料相当額を厳密に計算する必要がある、と一貫しておっしゃっていると受け止めました。
私の中では、賃貸料相当額は賃貸管理会社や役所で確認すれば厳密に計算できると考えているので、そこが論点ではありません。
タックスアンサーNo.2600の記載通りに、賃貸料相当額を計算してそれを超える自己負担もした時に、50%どころかかなり少ない自己負担額で済むと予想されるが、自己負担額以外の部分を法人が経費で計上し、それを税務調査で否認される理由があるのか、を知りたいのです。
法的な理由が無いなら、単に賃貸料相当額の計算が煩雑だからやらない、という税理士さん側の理由だけになってしまいますが。
如何なものなのでしょうか。
小規模な住宅で、タックスアンサーNo.2600の2の通りに計算した結果の賃料相当額が家主に支払われる賃料の1割であったとしても、国税庁が示した計算方法で計算している限り否認はされません。
計算の為に必要な固定資産税評価額課税標準額などの資料を集める責任は納税者側にあるのであって、税理士にあるのではありません。
ご質問者様か医療法人が計算に必要な資料を集めて、税理士に計算を依頼すれば済む話です。
ご回答ありがとうございます。
タックスアンサーに書いてある以上の縛りは無いという事で宜しいですね。
もちろん資料集めまで税理士さんが依頼される義務はないと考えますし、税理士さんにとっては何のメリットも無い余計な仕事になってしまいますので当然です。
大体スッキリしました。参考にさせて頂きます。迅速丁寧に何度もご回答頂き心から御礼申し上げます。機会がありましたらまた宜しくお願い致します。
国税庁が公表している以上のことはありません。
一つ付け加えますが、固定資産税課税標準額で計算する場合、固定資産税評価額の見直し(3年毎)に、賃料相当額を計算し直す必要があります。
それは知りませんでした、細かいところまでご教示ありがとうございます。
本投稿は、2021年07月08日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。