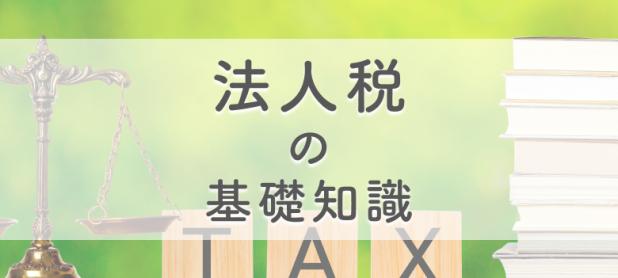法人税:【給与負担金の取り扱いについて】
タックスアンサー5245の読み方についてお訊ねします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm
【状況】
現在、当社一般従業員が関連会社に出向しており、当社から当該従業員に支給した給与(給与明細等は当社にて作成しています)・賞与相当額を給与負担金として出向先会社から支払ってもらっている状況です。
しかし、当該従業員が出向先会社において役員となっており、その取扱いについて混乱しております。
【質問】
出向先会社の経理において、当該従業員に係る給与負担金額は、出向先会社の役員報酬として、定期同額の届出等をしていない場合損金不算入になってしまうのでしょうか。
上記タックスアンサーを読むと、「出向者が出向先の法人において役員となっている場合」の2つの項目のどちらにも該当すれば損金不算入の規定が適用され、該当しなければ適用されない(一般従業員の給与負担金と同様に全額損金として計上できる)というふうに読み取れるのですが、いかがでしょうか。それとも、提示された2つの項目のいずれにも該当したうえで定期同額の手続き等をしなければ、いかに出向元が一般従業員として支払い、それを出向先から返還してもらっているだけであったとしても役員報酬・賞与とみなされてしまうという意味なのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
役員報酬(給与)において「定時同額」の届出という手続きはありません。ただし、役員賞与などを支給する場合の「事前確定届出給与」の届出はあります(定時同額ではないが、事前に確定した給与としての支給)。
そこで、
タックスアンサーに記載された(1)及び(2)の要件の両方に該当する場合
その支給される役員報酬が「定時同額」であれば、特に手続きをすることなく、出向先で「損金算入」できます。
なお、お尋ねの文章から推察しますと、「賞与」の支給があるようですので、この場合には「事前確定届出」の提出が必要になると思われます。そこで、届出書を提出し「事前確定届出給与」に該当する場合は、出向先で「損金算入」ができます。
さて、誤解があるようですが、法人税法第34条(役員給与の損金不算入)の規定とは
「法人が役員に支給する給与のうち
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③損金算入の要件を満たす利益連動給与の
いずれにも該当しない場合、損金に算入しない」とする規定となります。
「『いずれにも該当しない場合』、損金に算入しない」のですから、『いずれかに該当』すればいいことになります。
そこで、出向者が出向元で役員となり、出向先が負担している「給与負担金」が(1)及び(2)の要件に該当している場合において、その出向者が得る役員報酬(給与)が、給与のみ(定時同額)であるか、賞与等の支給があるかにより上記の「①」又は「②」に該当するか否かを判断し、手続き等をすればよいことになります。
米森先生
大変丁寧なご説明、ありがとうございました。よく理解できました。
重ねての質問で恐縮ですが、当方の事情の場合、いかに当該職員への報酬は弊社従業員として支払っていたとしても、出向先での役員報酬として取り扱わなければならないということでしょうか?
補足しますと、弊社従業員への報酬でしかないという認識で支払っていましたため、報酬額は定期同額ではなく、賞与も一般従業員同様、当該職員の業績等を考慮し算定した額を支給していましたので、タックスアンサーの1.2.どちらの要件にも当てはまらず、また、業務量や内容によって毎月給与額が変動するため、同じ額を定めるというのも難しい状況です。

米森まつ美
回答します
出向者はあくまでも「出向先では役員」であるいじょう、出向元では「従業員として支払っている」としても、法人税法上「給与負担金」は出向先の給与として取り扱われており、かつ、出向先で役員であるならば「役員給与の損金不算入の規定」が適用されます。
なお、出向者の役務提供は出向先であり、そのため給与の支給が出向元であっても、出向先では「給与負担金」を出向元に支払うこととなっているのです。
仮に「給与負担金」でなく、同様の金額を出向先が支払っているならば、その給与が「役員給与の損金算入できる」支給形態でない場合には損金算入はできません。このことからも「支払者」が出向先であれ、出向元であれ、役員が役員の役務提供に伴う給与には制限があるのだと考えられます。
改めて解説します。
役員の就任には「株主総会」等の選任決議が必要になりますし、役員給与も同様となります。
そのため、役員の出向に関しては一般の従業員の出向に比べ大きな違いあります。
法人税法上では、給与負担金を出向先法人の給与とすることを明確にし(法人税法基礎通達9-2-45)、役員部分については2つの要件(法人税法基礎通達9-2-46)を満たす場合に限り、法人税法第34条を適用するという取扱いになっています。
そこで、今回の「給与負担金」は、2つの要件を満たしておらず、また実際に支給された報酬(役員給与)は「損金算入できる役員給与」のいずれの要件にも該当しないため、出向先が出向元に支払う「給与負担金」は、出向先の損金算入することはできないと解されます。
なお、役員には「使用人兼務役員」となる者もおり、この場合「使用人相当額」は、仮に変動があっても損金算入となります。
しかし、「使用人兼務役員」を出向者として受け入れる例はあまり聞いたことがありません。
米森先生
ご指導の内容、理解致しました。たいへん分かりやすくお示しいただき、感謝申し上げます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
出向には、出向元、出向先、出向者、3者の合意が必要になります。
出向者からすれば、会社の命令で他社にて勤務をするのであり、給与等の支給額やその支給方法が異なる場合不安が生じると思いますので、法令上の考え方に加え、会社が出向命令する根拠が必要と思われます。
出向に関しては出向元と出向先との「出向契約書」とは別に、当該従業員に個別の同意を得る必要があるのは前述のとおりです。
そこで、出向内容を当該従業員と具体的に協議して合意に達すれば出向は可能(個別的同意)ですが、出向のたびにいちいち対象従業員と個別に協議・合意しなければならないのは極めて煩雑なことです。
しかし、就業規則や出向規定をキチンと作成しておく、又は労働協約で出向義務等を定めておかなければ、会社は当然に従業員に出向を命じることはできません(包括的合意がない)し、出向の内容も具体的はなにも決まりません。
そこで、今後も御社では出向が予定されるのであれば、就業規則等の整備が重要となります。また、その際には、出向先に従業員で出向する場合と役員として出向する場合の違いなども明示する必要があると思います。
なお今回は既に出向が開始されていますので、顧問税理士に相談の上、出向先と御社で良く話し合いをするようにしてください。
出向先では「給与負担金」を損金計上できないことから、その分課税負担が増加することになります。
米森先生
今後の方策までご提示いただき、感謝の至りです。ぜひそのように致します。
本投稿は、2022年05月06日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。