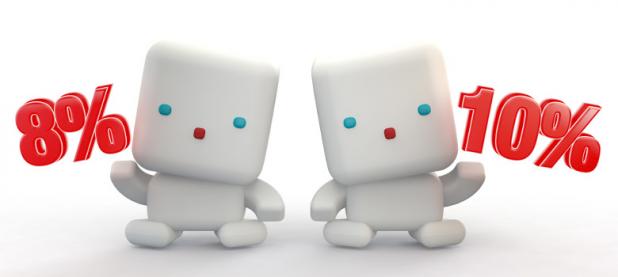元請業者が作成した出来高検収書について(インボイス制度)
元請業者が作成した出来高検収書を、下請業者に記載事項の確認を受けたうえで保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることが可能なようです。
当然下請けに確認は受けますが、消費税額を元請側で決めることに違和感があります。
これは、そもそも元請と下請の間で契約書や注文請書が存在し、そこで消費税額が決まっていることが前提の話でしょうか。
例えば、1,100,000円(税込)の契約書があったとして、出来高支払が5ヶ月間続いたとします。元請側で5回の出来高検収書を作者し、5回の消費税額が額が出てきます。その累計が契約書記載の消費税額と=になっていれば問題ないという認識で良いでしょうか。
考えすぎでしょうか。。。混乱します。
消費税額の端数処理(四捨五入、切り捨て、切り上げ)については業者によって様々ですが、元請側のルールで端数処理を行い、それを下請側が確認していれば問題はないということでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
工事請負契約のように、役務の内容が目的物の引渡しを要する請負契約に基づくものである場合の資産の譲渡等の時期は,原則として、目的物を引き渡した日となります。
従って,発注から引渡しを受けるまでの出来高払いは単なる中間金の支払いにすぎないこととなります。
ただし、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い,当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類(出来高検収書)を作成し,それに基づき請負金額を支払っているときは,検収時期においてその金額を基に売上代金が確定したもの(仕入税額控除ができるもの)とすることができることになっています。
要するに、おっしゃる通り、そもそも元請と下請の間で契約書や注文請書が存在し、そこで請負代金総額及び消費税額が決まっていることが前提の話です。
このため、下請業者に確認を受けたことによって、請負代金総額のうち、どの部分まで進捗したかどうかは下請業者が了解したとされるため、消費税額を元請側で勝手に決めることにはならないと思われます。
建築業界には、労務費だけの請負工事の場合に「出来高請求」といい、元請業者に対して、下請業者が完了前に1カ月間で稼働した出来形を慣習があります。
これと、元々請負金額総額等が決まっている工事請負契約の場合の「出来高検収書」とは別のものと理解する必要があるものと思われます。
本投稿は、2023年08月30日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。