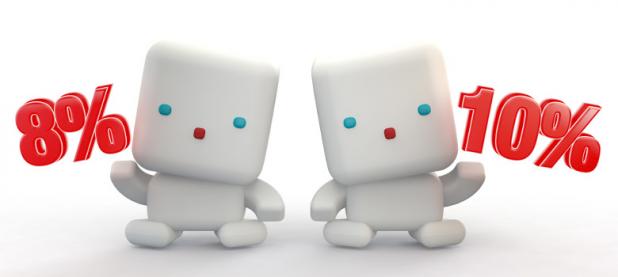製造小売業という業態について説明をお願いいたします!
個人事業主として小売りをしています。規模も小さいので意味はないと言われかも知れませんが、、。
さて、相談ですが、近々インボイス制度が施行される様ですが、自分自身も参加してみたい思いがあります。
…ですが、事業者同士が相互に申請登録されていなければ使えない制度ですよね。
小売り業の自分自身がインボイス制度を利用しようとする際に、仕入先が登録済みならば使える。これは理解しました。
ただ、そんなに都合よく仕入先が見つかる訳ではないですし、、(界隈では小売りは消費者向けだからほぼほぼ不要とまで言われてるみたいですし)。
その為、自分自身で製造小売り業をしてみたいと思っています。
一部の小物物品などは製作できるのですが、製造小売り業をするにあたり、、
製造小売り業とは何か。これまでの小売り業から製造小売り業に転業するにはどうしたら良いか?
そしてインボイス制度を利用するのにハンドメイド品等が通用するかどうか(適格請求書等)?
分からない事が沢山あります。説明と何かしらアドバイスをください。
税理士の回答

竹中公剛
…ですが、事業者同士が相互に申請登録されていなければ使えない制度ですよね。
相互は、関係はないと考えます。お金を支払う相手が、インボイスの番号を持っていなければ、・・・少し、消費税の控除額が少なくなるということです。
近々インボイス制度が施行される様ですが、自分自身も参加してみたい思いがあります。
消費税のことをしっかりと理解するうちは、安易に参加しないことです。
このメールでのやり取りは、難しいので、そこのところは、一切記載しません。
小売り業の自分自身がインボイス制度を利用しようとする際に、仕入先が登録済みならば使える。これは理解しました。
失礼になれば、お許しください。何も理解していないように思います。
仕入先が登録していなくっても、登録すれば、消費税を納める事業者になるということを理解ください。仕入れ先は関係ないです。
ただ、そんなに都合よく仕入先が見つかる訳ではないですし、、(界隈では小売りは消費者向けだからほぼほぼ不要とまで言われてるみたいですし)。
その通りです。売る相手が、消費者なら、扶養と考えます。
製造小売り業とは何か。これまでの小売り業から製造小売り業に転業するにはどうしたら良いか?
自分で物を造ることでしょう。
仕入れて売るのではなく、物を造る。
そしてインボイス制度を利用するのにハンドメイド品等が通用するかどうか(適格請求書等)?
通用の意味が解らない。
分からない事が沢山あります。説明と何かしらアドバイスをください。
多分ですが、番号は取らないほうが良いように思います。消費税は怖い法律です。
近くの税理士会などに相談ください。
確かに足をすくわれる形のご回答には思えます。税1つの話しも深掘りすれば知らない知識ばかりです。質問の仕方が悪いと思うしかありません。
1点、税なので、仕入税額控除というのがあると思います。仕入先の登録があるのとないのとでは違うと思っています。違うのでしょうか。

竹中公剛
1点、税なので、仕入税額控除というのがあると思います。仕入先の登録があるのとないのとでは違うと思っています。違うのでしょうか。
仕入先or経費の支払先に番号があれば、支払額の10/110の消費税を、控除できます。そうでない場合には、R8.9.30まで、80/110の控除ができます。
これは、こちらが番号をとるとらないかには関係はありません。
消費税を納める事業者の問題です。番号をとれば、自動的にん消費税を国に治める事業者になります。
簡易課税制度ですね。確定申告は複雑化したくない思いが伝わります!

竹中公剛
簡易課税制度ですね。確定申告は複雑化したくない思いが伝わります!
番号をとって、さらに、簡易課税制度をとれば、
多分ですが、製造小売業は、売上の消費税の3割を国に治める。
小売業は、個人に売る場合には、2割。事業者に売る場合には、1割を納める。
上記とインボイスの番号をとって、2年前が免税事業者なら、R8.9.30までは、2割特例という制度がある。

米森まつ美
回答します
近々インボイス制度が施行される様ですが、自分自身も参加してみたい
⇒ インボイスの発行事業者になるには、9月30日までに登録申請をする必要がありますのご注意ください。
インボイスの話の前に、消費税の仕組みなどを簡単に説明します。
1 消費税の申告納税の仕組みなど
消費税の申告納税は
売り上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかる消費税を控除した残額を計算(申告)し納税することになります。
「仕入れや経費にかかる消費税の控除」を「仕入れ税額控除」といいます。
この仕入れ税額控除は、仕入れ先などが仮に免税事業者(消費税の申告納税義務のない事業者)であっても、控除ができる制度となっています。(令和5年9月31日まで)
なお、消費税の申告納税は、基準期間(個人の場合は2年前)の課税売り上げの金額が1,000を超えた場合にその義務が生じます。(課税事業者)
2 インボイス制度
<改正の概要>
令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします
いままで「仕入れ税額控除」は、免税事業者からの仕入れなどであっても、仕入れにかかる消費税額を控除することができましたが、インボイス制度が開始されると、控除の対象とできるのは「インボイス」が発行された仕入等のみとなります。
[インボイスの発行をするには]
課税事業者であっても、インボイスの発行事業者の登録をしないと「インボイス」の発行はできません。
しかし、インボイスの発行事業者として登録した場合は、もれなく消費税の課税事業者=申告納税義務者 となります。
インボイスの発行事業者になり、発行事業者名簿に登録するには、「登録申請」を行わないと登録することができません。
なお、令和5年9月30日までに申請すれば「令和5年10月1日から登録」とすることができます。ただし、通知書がとどくまでは、個人事業者の方は登録番号がわかりませんので、この場合、通知が届くまでは「登録申請中」として通知が届きましたら番号をお知らせするなどの対策をとります。
[どのような問題が生じるか]
① 取引の縮小の可能性
今までは仕入れ先などが課税事業であるか免税事業者であるかは、すべて控除になりましたので特に問題になリませんでしたが、今後はインボイスの発行ができない事業者からの仕入れについては、躊躇される方が増える可能性があります。
あなたの取引先(売り上げ先)が、最終消費者であれば消費税の申告納税が関係ありませんので、特に問題はないと思います。
しかし、法人や個人事業者の場合には、あなたからインボイスの発行がない時には仕入れ税額控除ができなくなります(※)ので、インボイスの発行を求められたり、取引の縮小などがある可能性が生じます。
※令和5年10月1日からすぐに全額控除ができなくなるのではなく、経過措置があります。
② 登録した場合申告納税義務が生じる
インボイスの発行事業者になった場合は、もれなく申告納税義務が生じますので、その分の資金繰りなども考慮しないといけなくなります。
消費税の単直なやり取りに戻りますと、消費税は消費者が負担し、業者が申告と納税をするだと思っています。
標準税率10%ないし軽減税率の8%だとして????
簡易もしくは正規の適格請求書を発行するのには。。
登録番号を使い、自身が創作した製品を販売するのは適合するのからからは遠くなりましたね。製造御とかも言葉として耳にしますが、、
複雑な業態になると、開業し直しとかもあり得るのでしょうか??
米森様手取り足取りありがとうございます。

米森まつ美
回答します
>消費税の単直なやり取りに戻りますと、消費税は消費者が負担し、業者が申告と納税をするだと思っています。
⇒ そのようなご理解で間違いありません。
「消費税のための開業しなおし」は意味がないと思います。(個人事業から法人事業になる場合は別です)
実際の事業内容で、判断されることになりますし、個人事業の方の登録番号は事業内容が異なっていても、同一のものとなります。
改めて、インボイス登録の要否、簡易課税の選択の要否等々ご検討ください。期限が迫っていますので早急な判断が必要になります。
1 売上げ先との取引の検討
あなたの売上先が法人又は個人事業者である場合は、登録を検討される必要が少なからずあると思います。
例えば、貴方に仕事を依頼し製品を納入してもらい請求書を見たときに「登録番号」がないと、貴方が免税事業者又は登録が済んでいない方であるとであることが相手方にわかります。
その時の請求書に消費税額が別途記載されていた場合、相手側がどのような反応をされるのかご想像ください。
2 仕入れの検討
消費税の「売上」にかかる税額の把握は簡単ですが、仕入れ税額を確定することが大変な手間となります。
※ 税率は食品は8%、それ以外は10%なので、おおよそはその区分だけです。
しかし、仕入等に関しては
その仕入等(経費も含む)の税率、課税・非課税の判断、インボイス適用なのか、経過措置や特例を使用できるのかなど、これらを判断したうえで、記帳や申告をする必要があります。(いわゆる一般課税)
その手間を少なくする制度が「簡易課税制度」となります。
製造卸・・・加工などをして業者に卸す
製造小売・・・加工などをして消費者に販売する
これらの業種は、おおおよそ第3種に区分されます。(仕入れ税額控除は、売り上げの70%)
この簡易課税制度は「課税期間の開始前」に届け出をする必要がありますが、今回のインボイス登録により課税事業者にかる事業者は、令和5年9月30日までに届出書を提出すれば、今年から簡易課税を選択することができます。
更に、今回のインボイス導入により、登録により課税事業者になった方で、基準期間の売上高が1000万円を超えない場合は、「2割特例」・・・仕入れ税額控除額を売り上げにかかる税額の80%として納税額を20%とする特例・・・を利用することができます。
米森様、ならびに竹中様、ありがとうございます。頂いた回答を熟読し、検討に検討を重ねたいと思います。チャンスに対してトライしていく精神を忘れない様に。
馬鹿げた話しと思われるかも知れませんが、努力していきたいと思います。ありがとうございました!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
難しいかもしれませんが、ご検討ください。
登録申請し、登録番号が発行されるまでには時間がかかります。
e-taxでの申請なら、大体3週間から1ヶ月
書面の場合は、今は2ヶ月以上かかっているようですのでご注意ください。
※9/30までに登録申請をした場合は、請求書等には「登録申請中 番号が通知次第お知らせします」などと記載されるとよいと思います。
インボイスに記載事項も決められています。
記載事項が抜けている場合は、インボイスとしての効力がなくなります。
(特に適用税率や消費税額が記載もれとなっています)
簡易式のインボイスは、発行する事業形態が決められていますので、通常のバージョンで作成する必要があります。
以下の国税庁hpに掲載されたQ&Aをご確認ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
国税庁HPより関連する説明箇所を参考に添付します。
用語がわかり辛いと思いますが、よろしくお願いします。
「適格請求書等保存方式の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
「インボイスの記載事項」(Q&Aから)
「簡易課税制度の説明です」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
「2割特例」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
「インボイス特設サイト」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
本投稿は、2023年08月31日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。