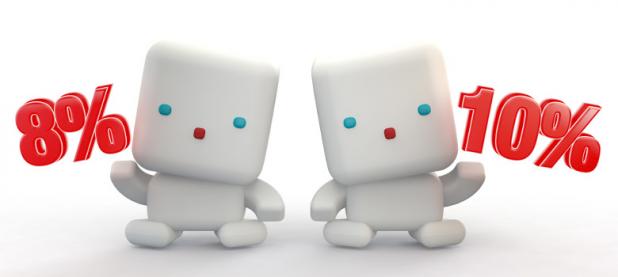消費税は直接税か間接税か
消費税は直接税ですか? 間接税ですか?
担税者と納税者が一致するかしないかにより、直接税、間接税と区分けされます。裁判例 H2.3.26 東京地裁では「消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない」と判示しています。ここからすると直接税と解釈して良いかと思いますが、正しいですか?
同裁判例は他にも以下のような表現があります。いずれも直接税を意味するものと感じています。「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない。」「消費税の納税義務者が消費者、徴収義務者が事業者であるとは解されない。」「事業者が納税義務者なのか、消費者が納税義務者なのかが不明確であるといった事情は認められない。」「消費者が消費税相当分として事業者に支払う金銭はあくまで商品ないし役務の提供の対価としての性質を有するものであって、消費者は税そのものを恣意的に徴収されるわけではない。」
間接税は入湯税やゴルフ場利用税があり、利用者の納税義務が明記されていますが、消費税法には消費者の語が一切出現せず、消費者の権利や義務が書かれていません。したがって直接税と解釈するのがすっきりします。
世に間接税であるとする解釈もあるようですが、そうであるなら、その根拠の明示を頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
税理士の立場として消費税は実務上の取扱いのみで考察しており、直接税であるか間接税であるかの定義は重きを置いておりませんので、関係各者の解釈等を述べさせて頂きます。
国税庁ではホームページに記載されている消費税の定義には、納税義務者について「国内取引の場合には、事業者は非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。」との内容で納税義務者は事業者だということしか記載されていません。(納税義務者=事業者 消費者?あいまい)
免税事業者ということで消費税を免除されているのに対して益税という考えに対して裁判所の判例では、「消費者は消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは言えない」「消費税の徴収義務者が事業者であるとは解されないため、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有さない」とされています。つまり事業者は預り金として消費者から消費税分を預かっているわけではなく、あくまで商品やサービスの付加価値として金銭を受け取っているということになります。(担税者つまり負担者=消費者≠納税義務者 徴収義務者≠事業者 消費税≠預り金 法律上の観点から)
税理士会では「直接税とは、納税者が国や地方公共団体に直接納めるもので、担税者(税金を負担する人)と納税義務者(税金を納める人)が一致します。例として所得税・法人税・相続税・住民税などがあります。間接税とは、担税者が直接税金を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納める租税で、消費税・酒税などが該当します。」との定義とその対象税目としています。(担税者つまり負担者=消費者≠納税義務者=事業者 消費税=間接税 実務上の立場から)
税理士会の租税教育の中では、「消費税は消費者が負担する税で、事業者に負担を求めるものではありませんが、消費者が何か物品を購入したりサービスを利用したりするたびに税務署に税金を納めるというのは、現実的に不可能です。そのため、小売業者や卸売業者などの事業者が、消費者に代わってまとめて納税する仕組みになっています。消費者が納税する税金分は、事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せされて、製造業者から卸売業者へ、卸売業者から小売業者へ、小売業者から消費者へと次々と転嫁され、最終的に物品の購入やサービスを利用した消費者が負担する仕組みとなっています。消費税を次々と転嫁するプロセスを踏むことによって、消費者が事務負担なく消費税を納税できる仕組みを実現しています。」と記されています。(課税システムの考えから)
インボイス制度の下では売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える必要があります。取引における正確な消費税額を把握することができますので、上記の課税システムがより精度が高いものになり、消費者への転嫁の状況及び中間の事業者の納税事務等の計算内容が詳しく確認できると考えます。(インボイス制度の功罪)
法的な位置づけは曖昧な部分がありますが、課税システムとして考えるならば消費者に負担を課して、事業者が納税事務を行う「間接税」との位置づけであると考えます。
回答ありがとうございます。概ね理解しました。ただし疑念が残っています。
担税者という語の意義です。ご回答内に担税者とは税金を負担する人とありましたが、負担の意味が H2.3.26 東京地裁裁判例でも "実質的に" 負担するという表現をとっており、これが意味するところは「現実の商取引の中ではお金を実際に支払っているのは消費者です」ということで、それを担税者と表現することに違和感を抱きます。担税者の本来の意味は、税の負担義務を担うべき者と考えるべきかと思います。この意味で言うと、消費者は財やサービスの代金内に価格転嫁された消費税分の代金を支払わされているだけであって、消費者自身には納税義務はないはずです。それが証拠に先の H2.3.26 裁判でも、消費者による不服申立制度の不在が立法として不十分であるとする争点もありましたが、これも消費者が納税を義務付けられている者ではないため、立法に違法性はなしとして却下されています。
担税という言葉遣いのあやふやさ、そして直接税、間接税の定義の曖昧さが、本質問に対する回答の困難さに繋がっているかと思っています。
私の感じているところとして、商慣習や取引の実体を見れば消費者が実質的に負担していることから間接税、一方、法学的あるいは法理としては、あくまで事業者が税を担うべき当事者であることから直接税と考えるのが自然と思います。
ご教示頂ける内容があれば、再度ご返信を賜れば幸いです。

小川真文
「租税法律主義」とは、租税を賦課徴収する場合には、必ず議会の制定した法律に基づかなければならないとする考え方のことですが、消費税はこの要件を具備していないのではないかとの議論がありました。(以下国会質問から引用)
間接税については、講学上「租税負担の転嫁が行われ、法律上の納税義務者と租税の実質上の負担者とが一致しないことを立法者が予定している租税」といわれている。消費税も、間接税として、右のような「転嫁」が行われることが当然に予想されていると言える。
しかし、法は法として存在する形式すなわち公布された法律の条文の形態において、その規範内容が解釈確定されなければならない。講学上の間接税の定義が直ちに法の解釈を規律するものではないし、また立法意思といえども法の客観的存在形式を超越して、法の解釈基準となるものでもない。
このような観点から消費税法を検討した場合、「転嫁」の法律的必然性、事業者から消費者への租税負担の転嫁が法律上の義務として関係者に課されているという事態は、認められないと考えられる。何故なら、消費税法の条文には転嫁に関する直接的規定は存在しない。それ故転嫁の必然性を法的に導き出すことはできない。税制改革法には転嫁に関する条項が存在するが、「事業者は、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする」との規定は、転嫁が事業者にとって取引の一般的常態であることを宣言したにすぎず、転嫁を事業者の法的義務としたものとは考えられない。
要するに消費税法の規定の下において事業者は、消費税を消費者に転嫁するか、それとも納税義務者として自己の経済活動の枠内において消費税を自己の負担とするか、両者の選択は全く事業者の自由とされていると言わねばならない。政府が行っている転嫁に関する諸施策は転嫁が事業者の法的義務とされるかのごとき立場に立っていると言わねばならない。事業者は国民の一人として、「法律の規定なくして国法上の義務を負担することはない」とする憲法の法治主義の原理からみて、違法な負担を迫られているものと言わざるを得ない。
消費税法はすべての国民に対し、国民生活の全領域にわたり、すべての消費・すべての役務の提供に消費税が課されることとなっている。従って国民は、「消費なければ負担なし」などという立場に立つことは不可能の状態に置かれることとなり、国民は生存を維持するためのすべての生活資料の購入に対し、負担金の支出を余儀なくされる法的状態に置かれることとなったのである。
この国民の受ける不利益は、消費税の転嫁が事業者にとって法的義務であるか否かとは無関係の問題である。事業者にとって転嫁が法的義務であるならばより一層明確に、それが法的義務でないと認められた場合であっても必然的に負担金の支出を強制されるからである。すべての国民が支出を余儀なくされる負担金については、その負担を課すことの法令上の根拠が明確にされなければならない。何故なら、国民は、財産権を侵されない憲法上の権利を保有しているのであるから、明確な法律の根拠なしに負担金の支出強制によって財産を喪失せしめられるいわれはないからである。
「商慣習や取引の実体を見れば消費者が実質的に負担していることから間接税」「事業者が税を担うべき当事者であることから直接税」の解釈は理解できますが、そもそも消費税は税法上の定義や根拠があいまいな状態で課税を処している不自然さがあります。ご指摘の通り「担税者」という概念は消費税の法的な観点では否定されるものとなりそうです。
本投稿は、2023年10月12日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。