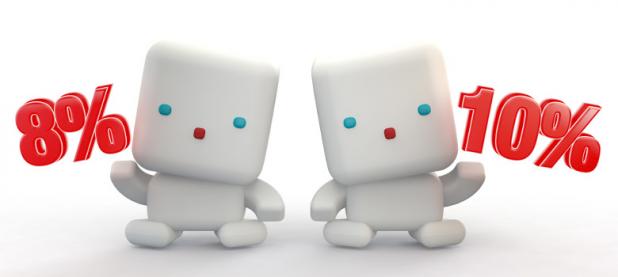月をまたぐ場合の役務の消費税率
運送の場合で、
今年9月発送10月着の月マタギの場合の運賃(経過措置非該当)の消費税率で、荷主が発送日基準、運送業者が着日基準を採用して消費税額計算をすることは妥当(可能)でしょうか。
税理士の回答
荷主への請求を旧税率でするのであれば荷主の発送日基準に合わせ、新税率で請求するのであれば役務提供完了時に合わせて荷主に新税率で仕入税額控除をしてもらうことになると思います。
類似の事例として収益・費用の計上基準が異なる場合について、以下の経過措置問3に記載がありますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf#search=%27%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27
どうも有難うございます。
事例では「売る方の消費税率に購入者側も合わせる」と読み取れましたが(買い手側の税率に売り手側も合わせてよいとは記載が無いので)、「売り手側の税率に合わせる」のが原則なのでしょうか。
課税仕入れの時期について、通達11-3-1を見ますと第9章の取り扱いに順ずるとされる為、売り手側が出荷基準で購入者側が検収基準でも認められるように思えますが、その場合税額が変わってしまうのですが、売り手と買い手がそれぞれ異なる消費税率で処理することは可能なのでしょうか。
Q&Aの要旨は、一つの資産の譲渡等について課税売上に係る消費税と課税仕入に係る消費財が異なるのはおかしいので同じ基準で処理すべきということと思います。
従いまして、荷主の仕入税額控除と運送業者の課税売上の税率が異なるのはおかしいと思いますので、上記の回答の通り、荷主への請求の税率に合わせて双方とも処理すべきと考えます。
なお、ご記載の通達関係は税率の変更がない状況での適用で、その齟齬を修正するために上記のQ&Aが示されているものと解せます。
消費税率は、売り手側と買い手側は一致することが原則ということですね。
分かりました、どうもありがとうございます。
本投稿は、2019年11月01日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。