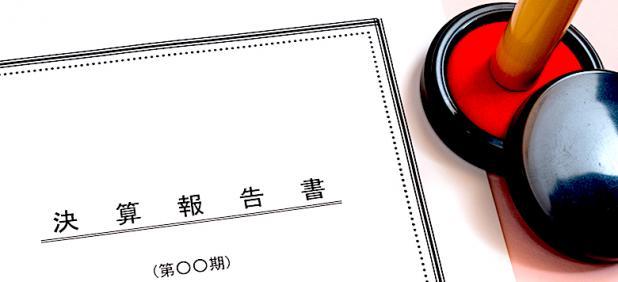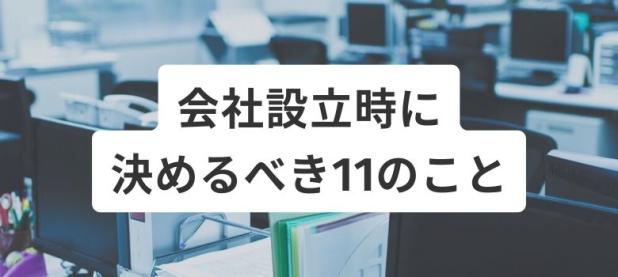法人成りの際の会計の引継ぎについて
個人事業(A店)を2017年12月で廃業して、2017年7月に創立した株式会社(B会社)に業務移管をしています。
A店の決算時に残った資産・負債の処理についてご相談です。
また、A店の事業主とB会社の社長が同一人物でCさんとします。
Cさんは女性でご主人(D氏)が別の事業をしています。
Cさんは2017年まで、個人事業の所得は少なく所得税非課税の範囲内だったのでD氏の所得税申告では控除対象配偶者になっています。
そこで、ご質問なんですが。
個人事業の2017年決算時の貸借対照表が以下のようになっています。
数字は概数ですが。
現金・預金 1,000,000 買掛金 850,000
売掛金 850,000 短期借入金 600,000
棚卸資産 420,000 未払金 1,200,000
工具備品 1,800,000 長期借入金 3,000,000
事業主貸 1,530,000 負債合計 5,650,000
資産合計 5,600,000
元入金 -290,000
控除前所得 240,000
資本合計 -50,000
負債・資本合計 5,600,000
売掛金・買掛金・未払金は、そのままB会社に引き継ぎました。
そこで、資産の方の現預金・棚卸資産・工具備品の処理なんですが。
そのまま引き継いでもいいのですが、B会社へ売却したとなると、Cさんの2019年の譲渡所得になるかと思います。
222万円の譲渡所得だと、D氏の控除対象配偶者にはなれないし、保育料の負担等もあって、Cさんの年間所得は100万円未満に抑えたいという意向です。
Cさんの年間所得を100万円未満に抑える策はありますでしょうか?
税理士の回答

Cさんが所有資産をB社に引き継ぐ場合、確かに譲渡収入が発生しますが、引き継ぎ時の帳簿価額が取得費(原価)となりますので、譲渡に伴う所得(利益)は生じない(ゼロになる)と思います。
従って、控除対象配偶者から外れたりすることはないと思われます。
なお、帳簿価額を超える価額でB社に譲渡する場合には異なる解釈となりますのでご留意ください。
こんにちは
詳細がわかりませんので、法人成りにおける一般的な資産負債の引き継ぎについて記載させていただきます。
1.売掛金、買掛金、未払金はそのまま引き継ぎで問題ありません。
2.現金預金については引き継ぎしません。
3.棚卸資産は通常販売価額の70%以上で法人に売却する形となります。通常販売価額は個人事業の時の販売価額を基にされれば宜しいかと思います。通常販売価額の70%未満だと定額譲渡となりますので、通常販売価額で販売したものとして所得計算がされますのでご注意ください。
なお、個人事業の時に消費税の課税事業者であった場合は、消費税を加算して法人に売却する必要があります。
4.工具備品は前年の確定申告書の減価償却の計算で記載した未償却残高(期末残高)から、法人に売却するまでの月数の減価償却費を差し引いた金額で法人に譲渡します。譲渡価額-帳簿価額=0となりますので売却益は生じません。これも棚卸資産と同様、個人事業が消費税の課税事業者であった場合は消費税を加算して売却した形となります。
5.短期借入金と長期借入金が金融機関からの借入であれば、債務者変更が可能か、又は、一旦個人借入を返済して法人で借入する形にするのかは、金融機関に相談する必要があります。
所得計算については、棚卸資産の法人への売却価額により計算する必要があります。後々、税務調査等で指摘を受けないようにするためにも、お付き合いのある税理士等に相談された方が良いと思います。
なお、法人成りと言いましても、売掛金や買掛金を含む債権債務を個人から法人に売却する形となりますので、売買契約書などの書類を作成されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
確認なんですが。
現預金は、廃業時点でCさんのもの(財産)としていいということですね。(引き継ぐ必要はない)
棚卸資産・工具備品についても、このままの価格で会社に売却すれば、Cさんの所得にはならない。その際売買契約書を作成しておいたほうが良い。
ということでよろしいでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
現預金はCさんの財産としていただいて結構です。
棚卸資産は、このままの価格というのが帳簿価額であれば違います。
繰返しになりますが、棚卸資産は、帳簿価額ではなく通常販売価額の70%以上で法人に売却する形となります。(70%未満では低額譲渡として、Cさんは通常販売価額で法人に売却したとして所得計算され、法人は購入価額と通常販売価額との差額が受贈益として益金参入されます。)
工具備品は、前述の通りです。
売買契約書は作成された方が良いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月14日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。