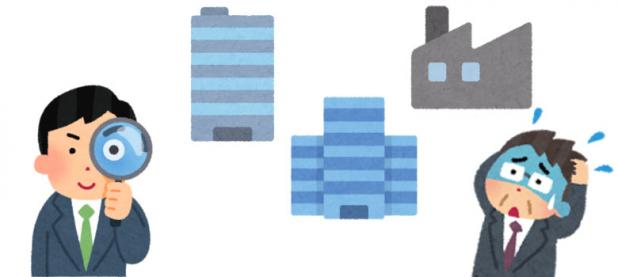相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用した人が
40年後に相続税の申告をし税務署が申告書に誤りがないか?当時から現在までを調査できるのですか?
税理士の回答
本来申告すべきだったのにもかかわらず、無申告で40年後に申告したということでしょうか?
そもそも、相続税申告は7年で時効になりますので、40年後に申告しても受け付けられません。
したがってその申告についての税務調査はありえません。
それとも相続時精算課税制度による贈与があってから、40年後に相続が開始された場合の相続税申告についてということでしょうか?
そうであれば、税務署において相続時精算課税選択届出書あるいはその記録がシステム上に保存されていると思われますので、申告内容の適否について検討されるでしょう。
相続時精算課税制度による贈与があってから、40年後に相続が開始された場合の相続税申告についてです。
なるほど!相続時精算課税制度を利用する際に申告してるから記録が残ってますね。
金融機関の顧客との取引履歴の保存義務期間は10年間なので税務署でも把握できないと聞いたことがあったのですが‥
全国民の銀行・証券会社の取引履歴は、永久にマイクロフィルムを使って税務調査できる。
という書き込みを見たので‥
でしたら相続税の申告の際に30〜40年前の口座履歴を税理士に提出が必要ですよね?
相続時精算課税制度による贈与があってから、40年後に相続が開始されて相続税申告漏れをマイクロフィルムで調査できるから筋が通るなと色々と考えていて
相続時精算課税制度を利用した人が
40年後に相続税の申告をし税務署が申告書に誤りがないか?当時から現在までを調査できるのですか?
という質問に至りました。
税務署は将来の相続税申告に備えて相続時精算課税制度の贈与事績を保存していると思われます。
ただし、相続時精算課税制度の贈与事績が税務署に保存されていることと口座の取引履歴が金融機関に残されていることとは別です。
たとえもしも金融機関に30年~40年前の取引履歴がマイクロフィルムで残されていたとしても、金融機関は保存義務期間超過による不存在を理由に税務署に開示することはないでしょう。
したがって税務署は金融機関で10年超の取引履歴を把握することはできないため、相続税申告書作成のために税理士に10年超の通帳等を提示する必要はありません。
スッキリしました。
中田先生!ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月16日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。