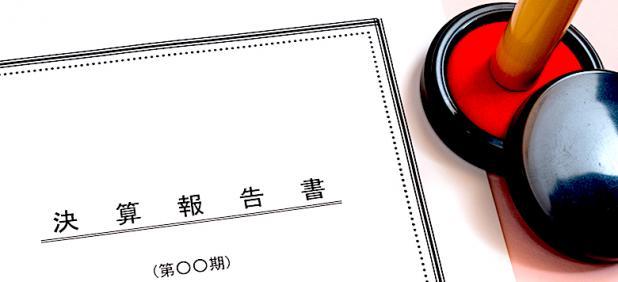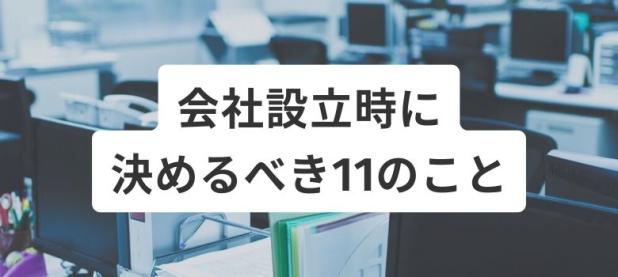個人塾の開業、税金について
現在、一回500円~千円で近所の勉強の苦手なお子さんを指導えています。今は 月に一万円~二万円の収入なので確定申告は気にしていませんでしたが、最近、希望者が増えてきました。今はそちらはお断りしてますが、今後お受けする場合は個人塾として企業すべきか悩んでいます。
今の時点での希望者を全員見てあげるとなると、月に60000~70000円ぐらいの収入になりそうです。
自宅の一室で教えています。月謝制ではなく、来てもらったときにお金を受けとる制度です。
いろんな申請、申告がめんどくさく、今までは小規模でやっていましたが、困っておられるかた、今みているかたのご兄弟を頼まれているので、そちらも気になって来て、今後どうすべきか悩んでいます。
しかし、開業届を出したとしても、公な塾にするつもりはなく、現在の方のご兄弟、知り合いのどうしても困っておられるかたしか見てあげるつもりもありません。卒業したりすると生徒もまた一人、二人に戻ると思います。
そして受け取りの領収書は発行してませんし、自宅の部屋なので実際の光熱費とかもわかりません。いろんな面を考えて今後どうすべきか悩んでいます。
税理士の回答

中西博明
個人塾は本業ではなく副業としてされているということでしょうか。
それであれば、事業所得ではなく雑所得になり、原則、開業届などの書類の提出はいりません。
また、税金の申告については、給与所得がほかにある場合、雑所得が20万円を超えない限り確定申告は不要ですが、住民税は20万円以下であっても申告が必要になります。
なお、雑所得は、収入から必要経費を差し引いて計算しますが、教えている部屋にかかる光熱費など業務に直接必要な支出は必要経費になります。
さっそくのお返事ありがとうございました。私は現在、主人の扶養に入っています。子供がよく病気をするので働きに出れず、この指導の謝礼が全収入です。暇なときに見てあげている感じで、予定していても、子供が病気になっていたり、生徒の方がドタキャンしたり…という具合で教えています。
扶養に入っていても、住民税の申告が必要でしょうか?何もわからず、とりあえず暇なときにちょっと教えてと頼まれて、その謝礼として一回500円、千円を受け取っている状態です。
今までの領収書もなく、いつ指導したかも、かかったコピー代なども全くわからない状態です。

中西博明
他に収入がないようでしたら、雑所得が35万円を超えない限り住民税の申告も不要です。
現段階では申告は不要という判断でいいと思いますが、仮に、今後収入が増えてくるようでしたら経費にかかる領収書などを保存するようにしてください。
何度もありがとうございます。
そして度々すみません
まだ確定ではありませんが、もし今希望してくださってる方を全てお受けしたら、それ以降は最高で月に6万~7万ぐらいの収入になる可能性もあります。その場合、確定申告がは必要になってきますが…
その場合は、いただいた謝礼に対し、いちいち領収書をお渡しして記録を残す?ことが必要なのでしょうか?
また家のプリンターでコピーしたものや、光熱費のうちわけ、100均でまとめ買いしている文具など(100均では領収書はもらえると思いますが…)はどのように証明すればよいのでしょうか?
わからないことだらけなので、確定申告が不安で、本来は今よりも収入は増やしたくないのでお断りしたいのですが、ご兄弟や知り合いの方のお子さんで、塾にもついていけず本当に困られてる方が多くて、それもかわいそうだし、と悩んでいるところです…
その雑収入の35万の壁で悩んでいたところに、収入がそこまで増えるなら開業したほうがお得なのでは、と教えてくれた方がおられました。ただその方も詳しくはなく、ではどうすべきだろうと…と悩んでいる次第です。

中西博明
事業所得というからには例えば「○○塾」という看板をあげたり生徒の募集広告をだしたりして、営利を目的とした活動をすることが必要です。
節税のために事業所得で申告するというのが、ネット上で広がってしまって誤解をされている方がいらっしゃいますので、ご注意ください。
なお、雑所得であっても所得計算のためには収入と必要経費を記帳する必要があります。業務に直接必要と思う支出は領収書を残す癖をつけてください。
再びありがとうございます。
そうなんですね。
その方もくわしくなさそうだったので、ネットで見た情報を教えてくださったのかもしれません。
私もややこしいことは困るので、なるべく35万を出ないように調整しつつ、万が一出た場合には確定申告に困らないよう、とりあえず、できる範囲の領収書と、あとは記録だけでも残してみます。
光熱費の問題は残りますが…
何度もありがとうございました。
本投稿は、2020年03月20日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。