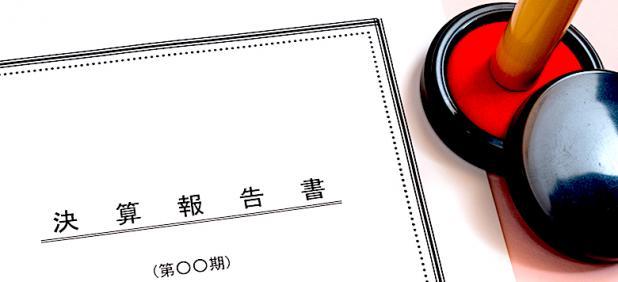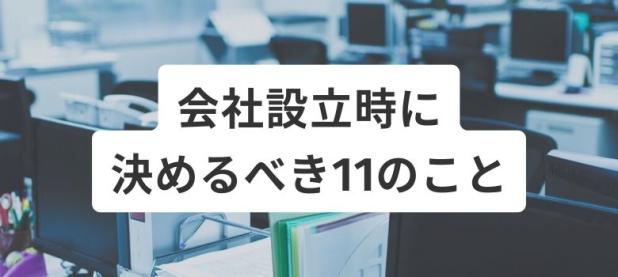会社分割
ひとつの同族会社を、構成する4人の株主の持ち株比率に応じて分割し、内1社を存続会社として継続し、他の3社を新設立会社として合計4社に分割することはできますか。
ごく最近、他の方が、同族会社1社をご都合で2社に分割することができますか、との質問に可能と回答されていました。
税理士の回答
会社法上、ご記載のような会社分割は出来ます。
但し、法人税法上その分割が税制適格となるか非適格となるかは別の問題となりますが、税制非適格だから出来ないということはありません。
前田靖様、
ご回答誠に有難うございました。
現在、個人での、所謂「一の者」はいません。
会社の正・負を含め、全資産を株主の持ち株比率に応じて、仮に分割できたとして、分割後各社が独自の経営で発足後、「税制法上適格」なのか「税制法上非適格」なのかということでどのような事態や差が生じるのでしょうか。
ひとつの同族会社を、構成する4人の株主の持ち株比率に応じて分割し、内1社を存続会社として継続し、他の3社を新設立会社として合計4社に分割することはできますか。
ごく最近、他の方が、同族会社1社をご都合で2社に分割することができますか、との質問に可能と回答されていました。
社法上、ご記載のような会社分割は出来ます。
但し、法人税法上その分割が税制適格となるか非適格となるかは別の問題となりますが、税制非適格だから出来ないということはありません。
会社分割などの組織再編において分割会社側で、税制適格であれば基本的に資産負債を帳簿価額で引き継ぐことになりますので譲渡損益が発生せず法人税課税が生じませんが、税制非適格の場合は資産負債を時価で譲渡したものとされますので内容によっては法人税課税が生じます。
組織再編税制の全てをネット上で説明することは困難ですので、実際の状況に応じて検討されている具体的なスキームを、直接税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
尤も、第三者間のM&Aは基本的に税制不適格であり、頭書の回答の通り会社法上は会社分割は自由に出来ます。
前田靖様
この度もご説明有難うございました。概念的にはわかってきましたが、
用語知識が乏しく、申し訳ありません。
基本的な事ですが、分割会社側が税制適格会社なのか税制非適格会社なのかの判定基準はどこかにあるのですか。
現在は1業種のみを営んでおります。分割後、各社は、同じ業種で異なる営業領域(顧客)を別々に経営することになります。
ひとつの会社の全ての資産を現株主毎(持ち株数の比率)に分割(分ける)して別会社にするのに、被分割会社(新設会社)にとってそれが、どうして「資産が譲渡される」ということになるのでしょうか。
一方、帳簿価格で全ての移行/引継ぎ(=分割)を行えば「適格(法人課税なし)」になる、、ということなのでしょうか。
税制適格・非適格の判定はその分割の具体的な内容によって、分割対価要件、主用資産等引継要件、事業関連要件、事業規模要件、経営参画要件、従業者引継要件、移転事業継続要件、株式継続保有要件、非支配関係継続要件など多岐にわたる要件がありますので、一言で説明することができません。
組織再編税制は、税理士などの専門家でも個別具体的なスキームごとに判断をする必要がありますので、誠に申し訳ありませんがこのサイトで全てを説明することは困難です。
前田靖様
度重なる質問にご回答をいただき、誠に有難うございます。
適格/非適格については多くの審査項目があることがわかりました。
これより、自分なりに研究してみます。
もしお差し支えなければ、更なる疑問発生の際はお伺いを立てたく、その節は宜しくご指導のほど
お願い申し上げます。
前田靖様、
度重なる質問申し訳ございません。
9つの要件につきまして、自分なりに調べてみました。「分割」と「合併」は各要件が同じ言葉ながら、相互に背中合わせに(表・裏関係)なっているようにも見えます。
分割する会社とされる会社双方にとって無駄なく分割するためには、この9要件が全て揃うことが「税制適格」を得る為に不可欠ということですね。
税制面でいえば、現在の会社経営の実態、株主/株数の関係、分割プロジェクトの主旨等を然るべき先生に診ていただくことですね。また、最初のステップでは、会社法としては問題はないとのことでしたが、会社法の下、プロジェクトを進めるには、会社法にお詳しい弁護士の先生にご相談なのでしょうか。
会社法上の問題は弁護士か司法書士、税制面では組織再編税制に詳しい会計士か税理士に、直接ご相談されたほうがよろしいかと思います。
前田靖様
早速にご返信いただき、誠に有難うございます。
複数回数に渡り誠意あるご回答を賜わり、感謝に堪えません。
弁護士または司法書士、会計士または税理士の件承知しました。
有難うございました。
本投稿は、2020年04月30日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。