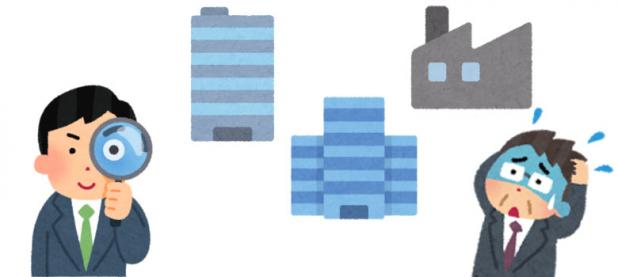棚卸の評価方法と届出の関係性
棚卸の評価方法についてご教示お願いします。
当方は小売業を営んでいる法人で以前から棚卸の方法を
商品を一つ一つ数えて商品別に単価と個数を掛けて算出していました。
商品別にしても仕入れた時期によっては単価も変わりますが、そこも
完全に区分けして商品別及び単価Aと単価Bとそれぞれの個数にて算出しています。
素人なので、よくわかりませんが”個別法”を採用していると思っています。
ただ以前に契約していた税理士さんの決算書には最終仕入原価法が個別注記表に
記載されていました。その流れで注記表も同じで申告はしていたのですが、
個別法と最終仕入原価法は計算方法が違う事を最近しりました。
これは税務調査等があれば否認されるものなのでしょうか?
棚卸方法の届出も先代から引き継いだ会社なので届出しているのかすら不明です。
届出がないと自動的に最終仕入原価法になるようですが、会社の実態を考えると
個別法の方が実態に沿うと思いますが、実態と棚卸方法が違う場合は実態は無視
されるものなのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
棚卸資産の評価に関しては、原則採用する評価方法を税務署に届け出る必要があります。なおその届出がなかった場合には、ご質問者様のご認識の通り、【最終仕入原価法】が採用されることとなります。
評価方法を変更する場合には、新たな評価方法を採用しようとする年の3/15までに変更する旨の届出書を税務署に提出することとなります。(本日当該届出書を提出しても新たな評価方法を採用できるのは、2025年分の確定申告から)
なので、税務署から調査があれば、最終仕入原価法による評価をしてください、と言われて過去の計算が否認される可能性もあります。(実態ではなく、形式で判断する)
一方で、税務署側は、過去の採用した評価方法による計算が実態に即していると認める場合には、その評価方法による計算を認めるケースもある、と税法上も明記されております。
なのでご質問者様の対応としては
➀所轄税務署に過去、棚卸資産の評価に関する申請書を提出していたのか、を確認すること。
②提出してないといわれたら、個別法の計算が実態に即している旨を説明したうえで、過去の計算および今後の計算の相談を税務署に行うこと
がよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございました!
やはり否認されるリスクはあるのですね・・・。
税務署のイメージは実態を重要視すると思っていましたが、そこは形式なんですね・・・。
アドバイス頂きました件、了解しました。
税務署に直接話す事は怖いですが、前に進まないので一度連絡してみます。
ありがとうございました!

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
在庫の評価に関しては、最終仕入原価法が不利、個別法が有利といったことはないですし、同じ商品の購入価額が大きく変動することもないかと想定されますので、何か指摘されて修正を求められても、多額の追加納付を求められるケースは考えずらいかと個人的には思います。
良きように着地されることを願っております。
失礼します。
最後のアドバイスを今、拝見しました!
最終仕入原価法と個別法に有利不利の差異があまりないものなのですね。
亀谷先生の経験上によるアドバイス、本当に助かります。
最後のアドバイスというか助言は私にとって救いの言葉でした。
一度、評価方法によってどこまで変わるのか検討してみます。
最後の最後までありがとうございました!
本投稿は、2024年04月12日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。