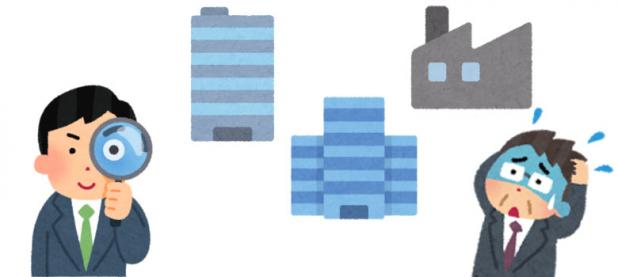税務調査が入り外注費について認められないと言われました
建築の仕事を20年以上している者です。
今回初めて税務調査が入ったのですが、私の知識不足から現金にて支払っていた外注費について領収証を貰っておりませんでした。
青色申告会を通じていつも申告しており、特にこの様な資料等が必要ですとの指示も無かったので、昔からの慣習で勤怠表のみの作成しかしておりませんでした。
既に辞めてしまった者とは連絡が取れなくなっており、税務署の方が調査したところ辞めてしまった者が確定申告している事実が確認できないので、その分に対して消費税、個人事業税、所得税等が400万ほど発生すると言われました。
間違った金額で申告をしていた訳ではないのですが、領収証が無かっただけで本来支払わなくてもいい税金を400万も払う事になるのは正直かなり金銭的に厳しい状況です。
この場合、何かいい手立ては無いものでしょうか?
無知が招いた結果とは言え、正直大変困っております。
税理士の回答
一般的な税務調査において、領収書のない経費を否認するかどうかの区分けは、結局のところは相手方を特定できるかどうかだと考えます。
調査官がどこまで真剣に確認するかにもよりますが、相手方が確定申告をしていないからこちらの経費を否認するという理屈は筋が違うと思います。
勤怠表に本人の筆跡が残っていたり、採用の時の履歴書などの書類から、支払った相手方の説明ができないか再度ご検討ください。
また、外注費とのことですので売上原価を構成するものと思われますが、仮に問題となっている外注費がすべてないものとした場合、原価率が大きく変わってくることはないでしょうか。その点からも外注費の支払いの事実を主張されてはいかがかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
履歴書等は貰っていなかったので、どの辺に住んでいた位しか分からずと言った状況です。
既に連絡も取れなくなっており、現在どこに住んでいるのかも不明です。
ただ、仰る通り原価率が大きく変わってきます。
また元請けからの入金遅れなどもあり、28、29年と事業資金の借入もしている状況です。
そもそもそれなりの外注費の支払いがなければ借入する必要もなかった資金です。
その2点を税務署に対し主張してみるのが得策でしょうか?
現時点で調査が終了しており、月末に税務署に出向く事になっております。
ご連絡ありがとうございます。
相手先の説明は難しいそうですね。
銀行借入をしたときの書類に借入の目的などが記載されてないでしょうか。そこに外注費の支払いに繋がる表現があれば主張の材料になるかもしれません。
銀行では融資をする際に社内で融資目的なども記載した稟議書を作成してますので、税務署に「銀行に反面調査をして融資の目的を調べてみてください」と事実を主張してもよいと思います。
原価率が大きく異なる点から外注費の支払いがあったこと、また、外注しなければ自分一人では仕事をこなせていなかったこと、外注費の支払いのために銀行借入までしていることを丁寧に説明し、そして今後は領収書等をしっかりと保存することを確約して(誠意を示して)、今回の外注費に関しては経費算入を認めてもらうよう、粘り強く交渉することが望ましいと考えます。
細かなアドバイスありがとうございます。
銀行の融資担当者にも連絡を取り、税務署の方にも反面調査の依頼をしたいと思います。
月末に税務署に行き手続きを進めていくことになっておりますが、それまでに可能な限りの対応をしていきたいと思います。
先日、税務署に行ってきました。
融資の件、原価率の件等話してきましたが。借入をしたお金が外注費として支払われたかどうか確認が取れない、原価率の件は分かりますが、とにかく外注費として支払われたか事実が確認できなきので経費として認められませんとの回答でした。
外注費を支払った職人さんが確定申告してないから、外注費とは認められない。
そもそも確定申告してない職人さんに非があるのに、全てこちらで税金を支払わなくてはならない事にも納得いきません。
実際、分割で税金を支払う事になっても月々10万程の金額を捻出する余裕すらないのが現状です。
税務署の方もその点は毎月のお金の動きを見て理解はしているようです。
このままだと自己破産の道を辿ることになりそうです。
少しでも納税額を減らす方法はないのか、再度アドバイスをお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
支払いの事実や支払い先の説明ができないのは確かに苦しい立場ではありますね。
今の調査担当者ではこれ以上の展開は難しいと思いますので、「分割払いでも納税はできない、このままだと自己破産するしかない」ということをお話しし、「従って、修正申告はできない。破産させたいのであれば更正処分してください。」と返すのがよいと思います。
「修正申告」は納税者自身が非を認めて自らが修正する申告です。そのため、一旦修正申告書を提出すると後で覆したり再度交渉することはできなくなります。
一方の「更正処分」とは税務署が職権で当初の申告を修正する手続きですので、不服申し立て等の手段が残されます。そして、更正処分するためには担当者は更正する内容や根拠をすべて文書で作成し、税務署内の幹部全員に説明するなど、とても面倒は手続きが必要になるため、それらの手続きを避けたいと思う担当者は否認金額を少なくして(妥協して)、面倒ではない修正申告に誘導しようとすることも考えられます。
調査担当者の指摘にどうしても納得がいかず、戦う気持ちがある場合には、修正申告に応じないで、更正処分をしてもらって次のステージ(審査請求や裁判)に持ち込むということ方法も可能です。この辺りは担当者の顔色を見て判断することになります。
税務署の最終判断が出ました。
減額しての修正申告となりました。
当初言われていた納税額の半分以下まで減額になったので、当方でも承諾をし修正申告をしてまいりました。
今後はどうのような形で分納するかを話し合うことになりました。
ある程度納得のいく形で終える事が出来ました事、アドバイスに感謝致します。
今後も何かとご相談させていただくことがあるかと思いますが、何卒宜しくお願い致します。
この度は、誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月24日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。