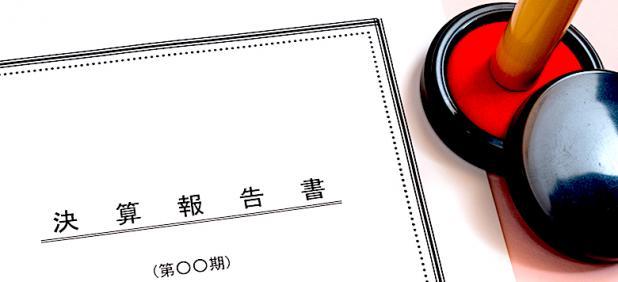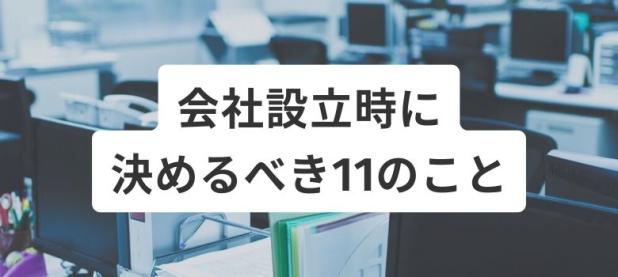個人事業主同士での仕事
個人事業主なりたての初心者です。
個人事業主同士で仕事を開始する際に必要なことは何でしょうか。
また、先方から売上金を振り込んで頂く口座は、私自身の屋号付きの口座で、そこからもう1人の個人事業主の者にお金を振り込む形を取りたいです。
もう1人の個人事業主にも、屋号付き口座を作らせるべきなのか、また相手が準備しなくてはいけないことや、個人事業主同士で業務委託契約を結ばなくてはいけないのか。
申告しなくてはいけないことや、知識が欲しいです。
お願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
個人事業主同士のお仕事が、民法上の組合として「共同事業」として行うものか、それともあなたが仕事を受けてもう一人の方は「外注」又は「従業員」となるのかを明確にしないといけません。
民法上の組合の場合は、「組合契約」を締結します。仕事は、この組合の名前で行うことになります。
その上で契約に従ってその収益等を配分(帰属)します。
外注の場合等は、「業務委託契約」又は「雇用契約」を提携する必要があると思われます。
この場合は、一旦全ての売上等を貴方の方で計上したうえで、もう一人の方への支払いを「外注費」として経費計上することになります。
所得(利益)の配分としては同じになると思いますが、例えば消費税の「課税事業者」に該当するか否か、また、「簡易課税の適用」ができるか否か」の判断をする際には大きく意味合いが変わってくると思われます。
共同事業の際には口約束ではなく、契約書を取り交わしお互いの責任や義務・権利について後々トラブルにならないように注意をすべきと思います。
なお、お相手の方に「屋号付きの口座」を作ってもらう必要はありませんが、それぞれ個人事業主として業務を行うのであれば税務署に対し「開業届出書」や「青色承認申請書」の提出をしてください。(青色は任意ですが、節税効果があります)
参考にしてください。
ご返信ありがとうございます。
外注の場合等は、「業務委託契約」又は「雇用契約」を提携する必要があると思われます。
この場合は、一旦全ての売上等を貴方の方で計上したうえで、もう一人の方への支払いを「外注費」として経費計上することになります。
とありますが、このどちらかの契約を結ぶ際は、何か書面などを国へ申告する必要などはあるのでしょうか。
また源泉徴収などはどうなりますか?

米森まつ美
契約の報告をする義務はありません。
ただし、雇用契約を締結し人を雇った時で、開業と同時の時は開業届出書の下部に、給与の支払い状況を記載する必要があります。開業と別なときに人を雇った時は別途「給与事務所の開設届出書」を提出することになります。
また、別途「失業保険」等の手続は必要となりますので、詳細は労働基準監督署などにお問い合わせください(社会保険関係は、社会保険労務士先生の業務のため申し訳ございません)
先の質問の回答の補則をします。
「雇用契約」の場合は、給与の支払になります。
※この場合の経費の科目は外注費ではなく給与となります。
「業務委託契約(外注)」の場合は、原則外注費になりますが、時間的・空間的拘束を受けるなど、その関係が「雇用契約に準じたもの」と判断された場合は、給与として処理されますのでご注意ください。
【源泉徴収について】
給与の場合
給与で「扶養控除申告書」の提出があるか否かにより、税額の計算方法が変わります。
例えば
「扶養控除申告書」の提出があり、扶養0人で社会保険料控除後の給与の額が10万円の場合
「源泉徴収税額表」の99,000以上 101,000未満の「甲欄」にあてはめると、720円の源泉徴収税額になります。
扶養控除申告書提出がない者の場合は、同じ金額の箇所の「乙欄」にあてはめると、3,600円の源泉徴収税額になります。
※ 「扶養控除申告書」とは、給与の支払いを受ける者が、雇用主に提出し、雇用主は当該申告書を保管する義務があります
外注費の場合
支払われる報酬が源泉徴収の必要となる「報酬・料金等」であるか否か、また、その支払われる報酬の内容により源泉所得税の計算が異なります。
また、個人事業主の場合、他に給与の支払がない場合は、報酬・料金等の源泉徴収の義務はありません。
例えば、
源泉徴収義務があり、その外注費の内容が「デザイン料」の対価の場合、100万円以下の金額の場合は、税率が10.21%になりますので、10万円の報酬の時には10,210円の源泉所得税額になります。
納付方法は、支払った翌月10日までに、所定の源泉所得税の納付書を使用して行います。
給与の場合は「納期の特例の申請書」を提出した場合、提出した翌月分の支払から年2回の納付とすることができます。
国税庁HPから参照なる箇所を添付します。
「源泉徴収税額表(月額)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf
「給与所得の源泉徴収税額の求め方」 3枚目(P21)参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/19-22.pdf
「源泉徴収のあらまし」(報酬・料金等の源泉徴収義務)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf
ご丁寧にありがとうございました。

米森まつ美
少しでも参考になれば幸甚です
本投稿は、2021年08月06日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。