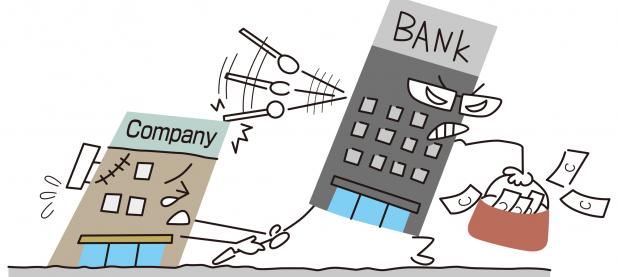決算少し前に休眠した時の今期の法人住民税の均等割りはどうなりますか?
知り合いが2年前に法人の会社を立ち上げました。決算月は4月で今期は利益はほぼ0円で経費のみが500万ほどかかっています。ところが最近その方が頚椎損傷し四肢麻痺となり、会社を畳むお金も無いのでみなし解散を狙って休眠会社とすることになりました。四肢麻痺で動けない為、特に詳しくもない私が手続きの代行を頼まれたのですが、その方は記帳もまともにしておらず、きちんとした決算書類は作れそうにありません。4月30日までには休眠するための異動届出書を提出する予定で、来期から法人住民税の均等割りは免除されることを役所に確認しました。
問題は今期のことで4月30日までに休眠してもやはり今期の決算書類は提出すべきですよね?
そうなると今期の法人住民税均等割りは支払わなければならないのですか?
もし今期の分の確定申告をせずにいたら、どのようなことになりますか?
何年も経って重加算税が加算されたりするのでしょうか?
休眠しても確定申告義務があるのは理解しているのですが、復活させる予定がないため、青色承認が取り消されても構いません。
どなたかお知恵をお貸しください。
税理士の回答
今期の均等割額の取扱いは自治体にお問い合わせください。
通常は、開業から休眠の日までは均等割額が掛かりますが、遡及して適用する場合もあるからです。
なお、法人税は休眠という扱いはありませんので、毎期決算と申告は必要です。(売上0、仕入や経費0、利益も所得も0での提出になりますが)
それ以前の問題として、ご質問者様が税理士でなければ、税理士法違反になります。
回答をいただき誠にありがとうございます。早速自治体に問い合わせてみます。
また税理士法違反とは、私が税務申告や異動届出書の提出などの手続きを代行することがそれにあたるのでしょうか?
会社の全ての権限を私に移行するという委任状を書いて貰っても、違反になりますでしょうか?
従業員の方に代行して貰ったほうが良いですか?
度々申し訳ありませんがご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士でない者が他人の求めに応じて税務署類の作成や税務相談をすることは税理士法により禁じられています。
ご記載のような委任状では有効になるとは思えませんし、当初のご質問(記帳もまともにしていない)から単なる代行ではなく、ご質問者様の判断で行うことになると思いますので、非税理士による税務代理行為として税理士法違反になります。
以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1
回答ありがとうございます。そうなのですね。そのような法律を初めて知り、無知で申し訳ありません。それでは私は税務に関することは代行できないのですね。
その場合、今期の確定申告を税理士の方にお願いするとどれくらいの料金がかかると思われますか?(資本金がいくらなのかも不透明な状態です。会社のお金と自分のお金がごっちゃになるという、かなりいい加減な経営をしていたようです。売上はほぼ0です)
また、税務署への確定申告の他に地方税についても各自治体に別途申告が必要ですか?
お忙しい中お答えいただいて大変ありがたく思います。またお時間できましたら、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
合わせて、その会社の従業員が経理事務の仕事として、税務書類を作成しても税理士法違反になりますか?
一般の方で税理士法を知っている方は稀かと思いますが、それ故に知らなかったでは済まされないから怖いものです。
税理士によって報酬は異なりますので、ご自身で個別にお探しいただくしかありません。(報酬基準はありません)
法人は、税務署、都道府県、市町村にそれぞれ申告が必要ですが、休眠届を提出していれば申告を不要としている自治体もありますので、自治体にお問い合わせください。
会社の従業員が税務申告書を作成するのは税理士法違反にはなりません。(上場企業などは社内で申告書を作成しています)
ご丁寧に大変ありがとうございます。行き違いになったようで最後にもうひとつだけ質問させて下さい。その会社の従業員が経理事務として会社の決算書類を作成したならば、それも税理士法違反になるのでしょうか?事務のパートの方が1人おり多少の会計知識はあるようなので、なんとか頑張って貰えればと思うのですが。。。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
会社の従業員が税務申告書類を作成することは、先に回答した通りです。
回答ありがとうございます(*^^*)
ご相談に乗っていただき、大変助かりました。
不透明だったことが全てクリアになりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月14日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。