建物と土地で所有者が異なる共有名義の居住用財産を売却した場合の3000万円特別控除について
現在、祖母・母・兄・私の4人で住んでいる家を解体して土地を分筆のうえ一部を売却し、その売却代金で残りの土地に家を建てる予定です。土地の所有者は「兄・私・母」建物の所有者は「兄・私・祖母」となっています。建物の持ち分がある兄と私はそれぞれが3000万の特別控除が使え、生計を同一にしている母に私と兄の控除しきれなかった余りを使えるのではと思っているのですが、以下の計算はあってますでしょうか?
売却代金:5000万
取得価格:証明するものがないため250万
譲渡費用:430万
5000-(250+430)÷3=1440
私と兄:1440-1440=0→課税なし
母:1440-(私と兄の控除しきれなかった分1440)=0→課税なし
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
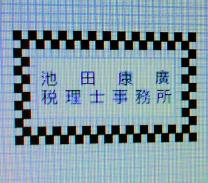
池田康廣
まず、譲渡価額を土地・建物に区分する必要があります。原則として3,000万円の特別控除を適用できるのは、建物所有者です。土地の所有者が同居している場合、建物所有者との合計での特別控除3,000万円まで特別控除が可能です。
計算はご質問のように総額で計算するのではなく、各人ごとに計算します。
建物所有者であるお兄さん・あなた・お祖母さんは問題なく特別控除ができますが、お母さんについては、お兄さん・あなた・お祖母さんの特別控除額の合計が3,000万円まで達していなければ、3,000万円との差額について、特別控除の適用ができます。3,000万円に達していれば、お母さんについては、特別控除はありません。
貴重なお時間を使って回答いただきありがとうございました。
母には税金がかかることになりそうですね。
解体して売却する場合でも譲渡価格を土地・建物に区分する必要があるのですね。
たとえばこのような考え方はできますでしょうか。
建物は築60年を越えており、固定資産税評価額は225万です。
私の建物持分は1/3です。私の持分のうち1/7を母へ贈与する。
12万以下となるので母は不動産取得税はかからず、登録免許税は3200円程度、
母も建物の持分がある状態になるのでその後建物解体のうえ売却すれば
私、兄、母の3人ともそれぞれ3000万の特別控除が使えるのではと
考えたのですがいかがでしょうか。
もしも再度ご覧になりましたらご回答いただけますと幸いです。
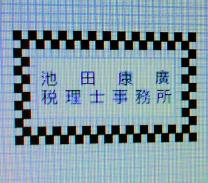
池田康廣
家屋を解体して売却する場合でも、3,000万円の特別控除の特例適用対象者は建物所有者のみです。このため、建物の所有権のないお母さんや土地と建物の持分か異なることになるあなたの譲渡価額を算出するためにも土地と建物の譲渡価額を区分する必要があります。また、譲渡前にお母さんに建物の持分をあなたから贈与すれば、3,000万円の特別控除の特例をお母さんも受けることができることになります。ご質問にはありませんでしたが、建物のみの所有者であるお祖母さんも3,000万円の特別控除の特例を適用することができます。
建物の固定資産税評価額225万円が時価であるかどうか検討を要するのではないでしょうか。もし、適正であるとすれば、土地の譲渡価額4775万円、建物の譲渡価額225万円で各人の譲渡価額は土地15,916,666円、建物はお兄さんとお祖母さんはそれぞれ75万円、あなたは642,857円、お母さんは107,143円となります。そして、全員が3,000万円の特別控除を適用することができます。
再度貴重なお時間をいただきありがとうございます。
木造で築60年越えのうえ、解体して売却するので祖母に譲渡所得が発生するとは思ってもいませんでした。気づかせていただきありがたいです。
「建物の固定資産税評価額が時価であるか見当を要する」とありますがこの「時価」を知るには不動産会社の簡易査定などの価格などでもいいのでしょうか。あるいは不動産鑑定士の方への依頼が必要なのでしょうか。
私の建物持分の一部を母へ譲渡することで全員が3000万の控除を使えるのであれば、建物の時価の評価額が高いものになっても大丈夫と思えるので、時価の評価額が高いものになるとしても出来るだけ簡易で費用のかからない方法で分かる方法があれば知りたいです。
自分なりに調べたところ建物の固定資産税額は再建築価格を元に算定しているとのことですが課税明細書から時価を読み解くことは出来るのでしょうか。
もしも再度ご覧になりましたらご回答いただけますと幸いです。
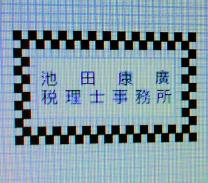
池田康廣
築60年超の建物ということですので、法定耐用年数(木造=22年ですが、これは事業用の木造建物で、非事業用の木造建物は1.5倍の33年となります。)は既に経過しておりますので、固定資産税評価額が高額と思いますが、お母さんが建物共有者となれば、共有者全員が特例適用要件に該当するので、これを採用しても問題ないと思います。
たびたびご回答いただき本当にありがとうございました。
思ってもいなかった気付きもあり大変参考になりました。
本投稿は、2023年02月03日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
























